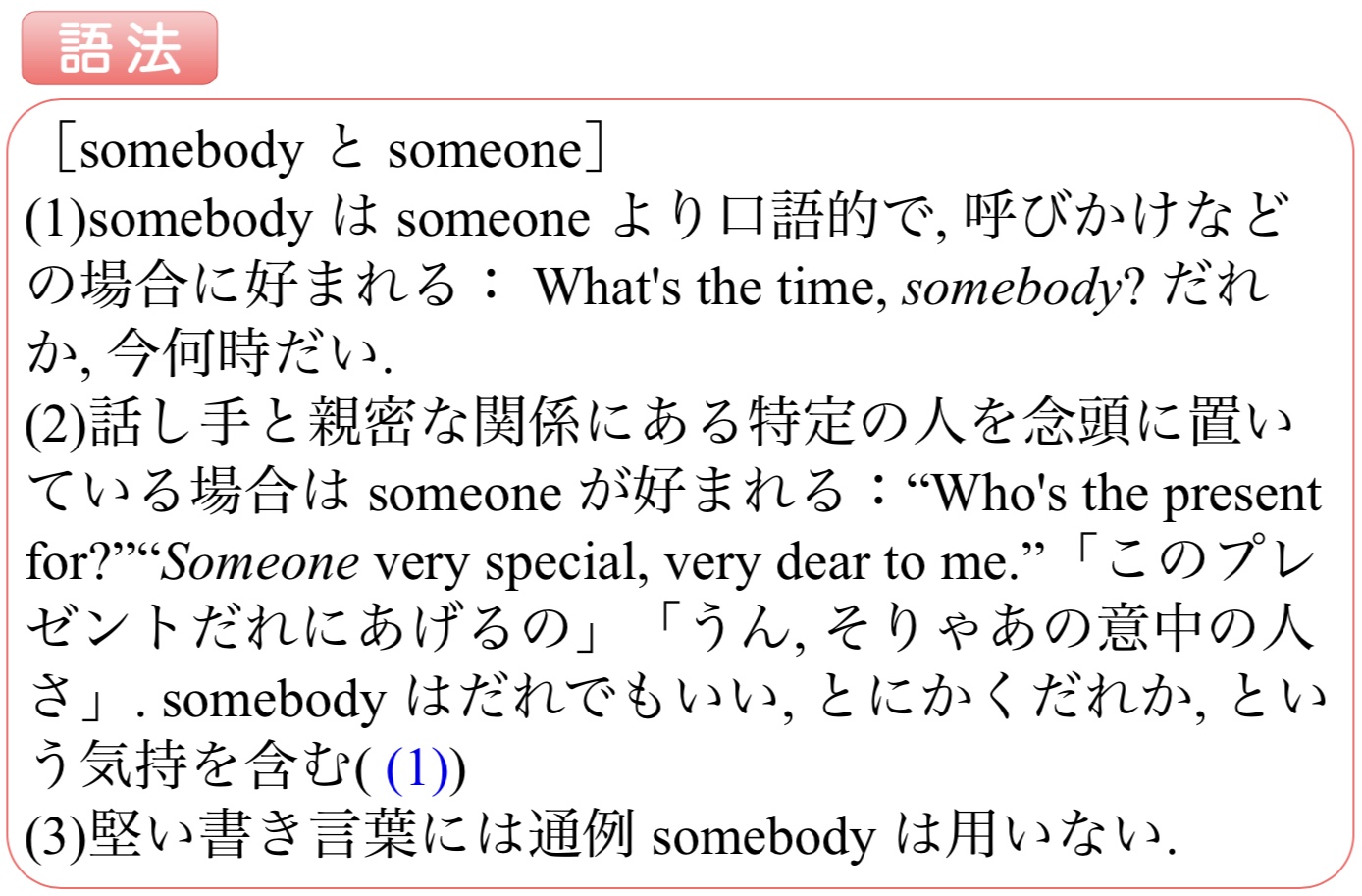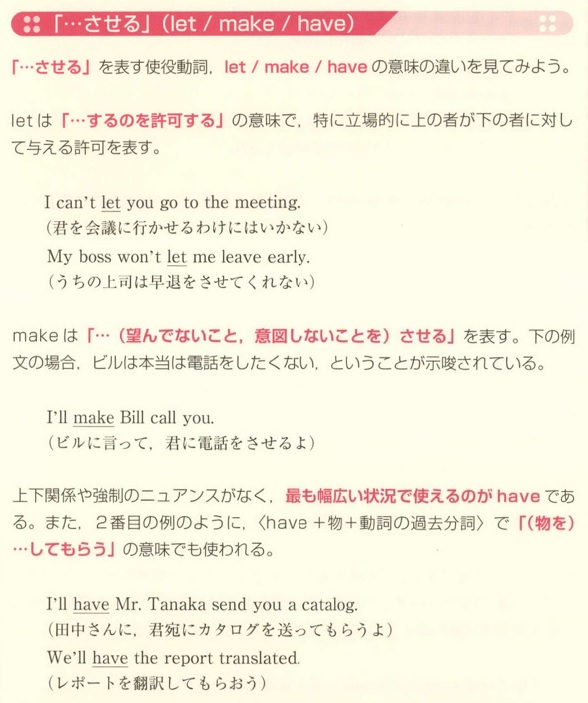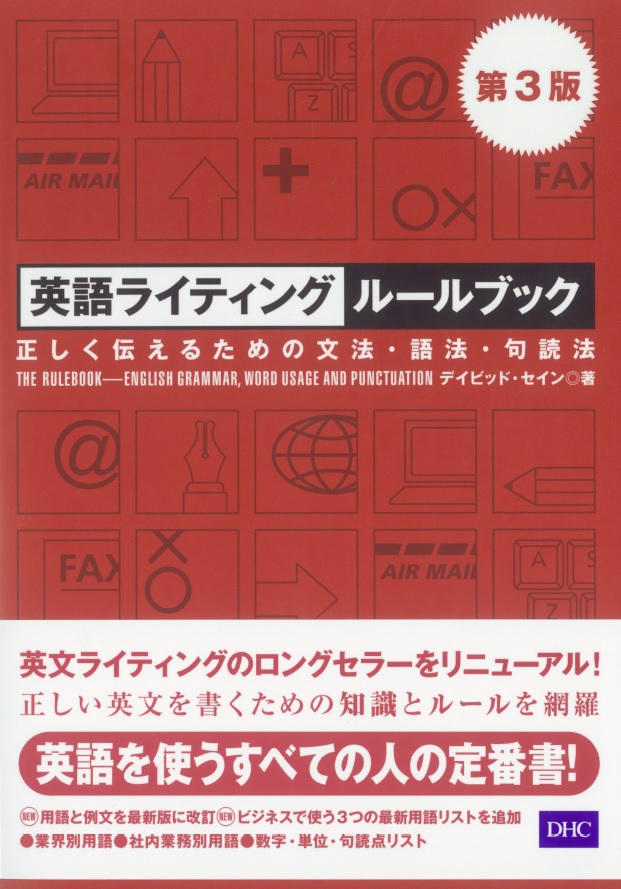Let somebody down
2025/09/18
~ をがっかりさせる、 ~ を失望させる
–
Don’t let X-san down.( Xさん をがっかりさせるな。)
–
待てど暮らせど、 納期遅れのスピーチ原稿が上がってこない。
–
高官の指定日に基づき、 なにもかも実行してきた。
なのに、そのご本人が肝心の 締め切り を守ってくれない。
多忙で不在。
とかく絶えがちな連絡。
皆目見当がつかない進捗状況。
–
「 ちゃんと着手しているのだろうか … 」
次第に疑心暗鬼が広がる。
–
「 いっそのこと、飛んで しまおうか … 」
やけっぱちな蛮勇が頭をもたげる。
–
度重なる約束破りに業を煮やし、 ついに意を決して、
高官直下の上役に相談に行った。
- 式典が目前に迫っています
- 早急に完成する必要があります
- 本当に困っているのです
- お力添えをお願いできませんでしょうか
焦りといらだちが募り、 ぎりぎりの本音を 吐き出した。
–
ー– 原稿がなければ、 翻訳者は身動き取れない
ー– 部下たちに、 原稿作成を委任( delegate ) できないものか
ー– そもそも、 ご自身で決められた締め切り日なのです
ー– このままでは、 翻訳する時間がなくなってしまう !
–
最後はもう半ベソ。
【参照】 式典の台本は、 脱線予防と時間厳守のため
◆ 幸運にも式典は無事終わり、 お口添えのお礼に参上。
すると、 恩人は得たり顔でにっこり微笑み、 こう述べられた。
–
–
I told him not to let X-san down.( Xさん をがっかりさせないよう、言っておいたんだ。)
–
間接目的語 ( X ) を入れた間接話法。
冒頭の表現をくるんだ、 ソフトな言い回しである。
だが、 “ let – down ” が分からなければ、 おそらく意味不明。
–
 –
–
約束は 守りましょう
–
–
ここでの 「 X 」は、私の名。
–
人称代名詞 ( personal pronoun ) ならば、
目的格 ( objective )の
me / you / him / her / us / them / it。
表題の “ somebody ” ( だれか )も代名詞。
上記の代表形の機能を有する。
いわば目的格のワイルドカード。–
–
代名詞 ” someone ” は同義であるが、以下の通り、
「 somebody は、someone より口語的 」。
” somebody ” も ” someone ” も、不定代名詞
( an indefinite pronoun )の複合語。
–
–
[ somebody と someone ](1) somebody は someone より口語的 で、
呼びかけなどの場合に好まれる。(2) 話し手と親密な関係にある特定の人を
念頭に置いている場合は someone が好まれる。
somebody はだれでもいい、とにかくだれか、
という気持を含む。(3) 堅い書き言葉には通例 somebody は
用いない。
––
–
『 ジーニアス英和大辞典 』
大修館書店、 2001年刊 ( ロゴヴィスタ アプリ版 )
… “ somebody ” の語釈より
<大修館書店HP>
–
英英辞典の見出しは、” somebody ” だらけ。
後掲のEFL辞典も同様。
略して、 ” sb “。
–
” someone ” は、語釈本文では使われるものの、
辞書見出しは慣習的に ” somebody ” 中心となっている。
–
◇ 「 人称代名詞 」 の解説は、 ここが秀逸 ↓
ーちょいデブ親父の英文法 「 人称代名詞 」
–
–
◆ ” let somebody down ” で鍵を握るのは ” down “。
【発音】 dáun (1音節)
日本社会にも久しく根付いている ” down “。
常日頃から見聞きするため、すんなり把握しやすい。
よい機会なので、これから深堀りしてみたい。
” down ” の語源は、 古英語 「 丘を下って 」( dūne )。
この 「 下って 」 を引き継ぐ英語 ” down ” の基本的意味は、
国語辞典の 「 ダウン 」 がほぼ網羅する。
–
ダウン【down】
- 1. 下がること。落ちること。
2. ボクシングで、倒れること。
3. 疲労・衰弱して倒れること。寝込むこと。
4. コンピューターなどが、故障・事故で働かなくなること。
5. 野球で、アウトと同義。
6. 主に球技の試合で、差引き一定数を負け越していること。
7. アメリカン・フットボールで攻撃の一単位。
ファースト・ダウンからフォース・ダウンまである。
( 広辞苑 第七版 )
– - 1. 下げること。 下がること。 引き下げ。 値下げ。
2. 〔 ボクシング 〕打たれて たおれること。
3. 病気・過労などで たおれること。
4. 〔 機械が 〕故障で動かなくなること。
( 三省堂国語辞典 第八版 )
–
◆ 英語 ” down ” は非常に多義である。
それでも、次の基本的意味は、下方へ向かう方向性を保つ。
- 副詞
「 下へ 」「 下がって 」「 落ちて 」「 向こうへ 」「 落ち込んで 」
「 寝込んで 」「 停止して 」「 書き留めて 」「 アウトになって 」 - 前置詞
「 ~ の下へ 」「 ~ に沿って 」 - 形容詞
「 下にある 」「 停止した 」「 倒れている 」「 落ち込んだ 」 - 名詞
「 下降 」「 倒れること 」 ※ 可算名詞 - 他動詞
「 降ろす 」「 撃墜する 」「 沈める 」「 飲み干す 」 - 自動詞
「 降りる 」 ※ まれ
–
◆ 物理的・状況的・精神的に「 下がる 」「 落ちる 」ことが、
” down ” の基本。
したがって、語感は総じて重くて暗め。
例えば、大型台風の際に飛び交う表現が、
- “The electricity is down.”
“The power is down.”
(停電している。) ※ ” out ” も可
– - “Trees are down.”
(木が倒れている。)
– - “Trains are down.”
(電車がとまっている。) ※ ” out ” も可
–
◆ ” down ” を漢字1字で表すなら、「 下がる 」の「 下 」よりは、
「 落ちる 」の「 落 」の方が、ここでは的確かも。

この代表例が、“ fall down ”( 下へ落ちる )を名詞化した
” downfall “。
図を再掲すると、
■ downfall ( 転落、 没落、 失脚 )
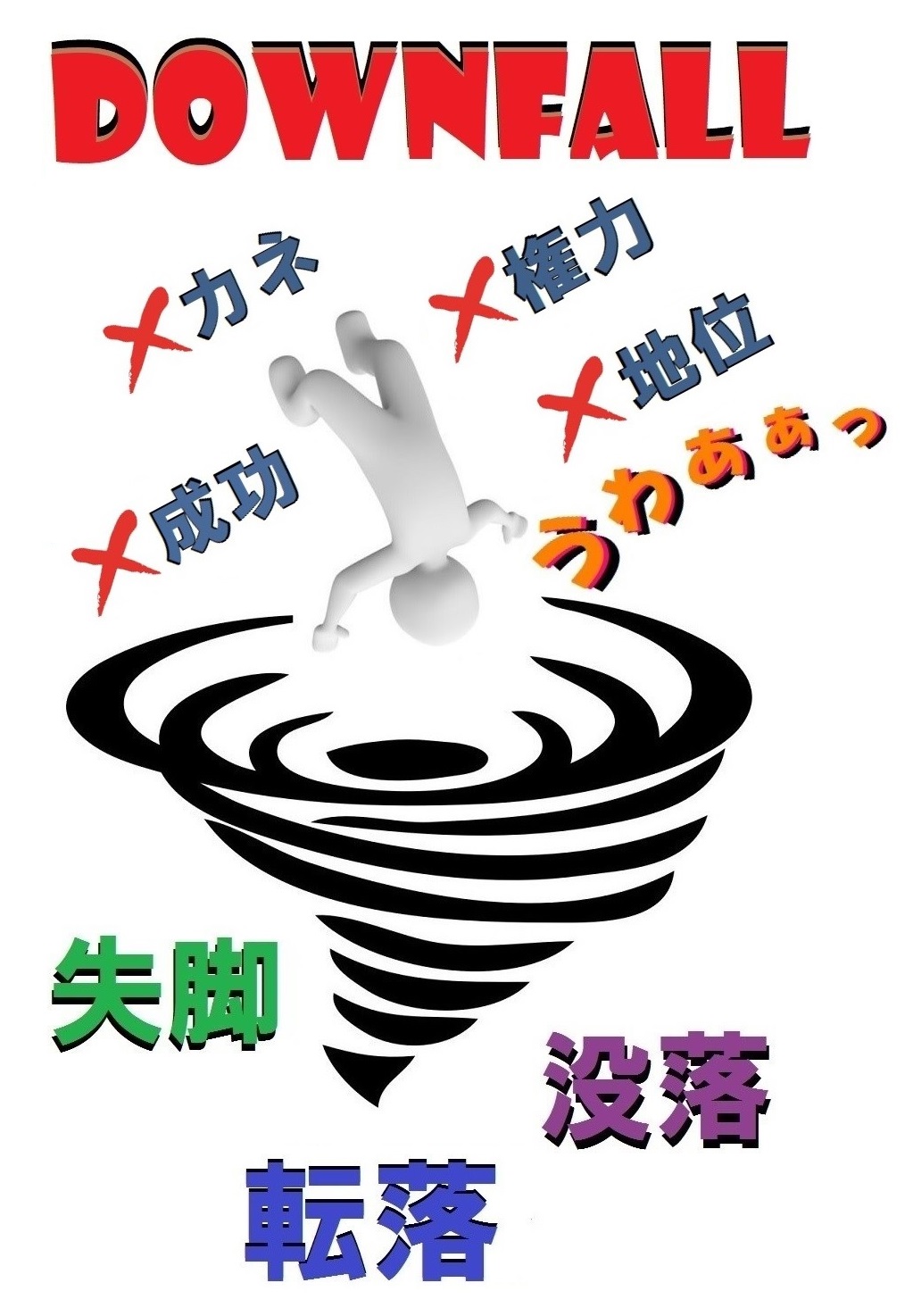
–
おまけに、
■ bog down ( 行き詰まる、 動けない )

–
■ step down ( 辞任する )
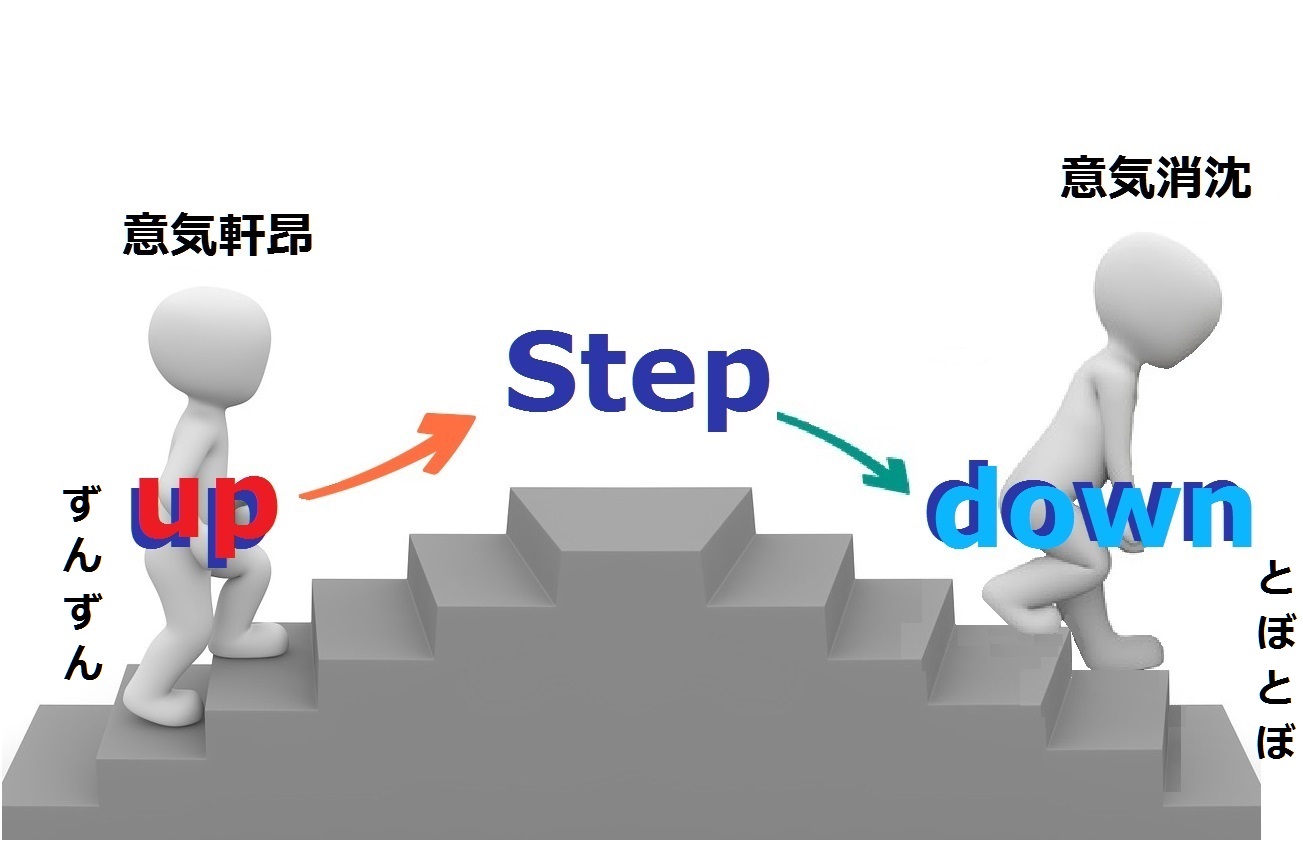
–
–
◆ こうして救いのない図ばかり見せつけられると、気が滅入る。
–
そんな落ち込んだ気分こそ、” let somebody down ” の ” down “。–
すなわち、自分の希望・期待にそぐわぬ結果に落胆すること。
–
使役動詞 ” let “( 後述 )に続くと「 ダウンさせる 」となり、
「 落胆させる 」 「 失望させる 」。
–
もっと平たく言えば、「 がっかりさせる 」。
以下、全文。
がっかり
- 失望・落胆し、元気をなくすさま。
( 明鏡国語辞典 第三版 )
– - 1. 事が思いどおりにいかず、気落ちしたさま。
2. 疲れて元気をなくしたさま。がっくり。
3. がっくりに同じ。
( 大辞林 第四版 )
– - 失望したり つかれたりして、ひどく元気がなくなるようす。
( 三省堂国語辞典 第八版 )
–
◆ 句動詞 ” let down ” が名詞になったものが、 ” letdown “。
ハイフン入りの複合語 ” let-down ” と表記することもある。
–
【発音】 ˈlet.daʊn
【音節】 let-down (2音節)
- 落胆、失望
- 低下、減少
- ( 着陸前の飛行機の )降下
同義語の筆頭は ” a disappointment “。
- “That job was a letdown.”
(その仕事にはがっかりした。)
– - “The investigation was a letdown.”
(調査は期待外れだった。)
– - “It feels like a really big letdown.”
(めっちゃがっかりした感じ。)
” let somebody down ” の場合は、目的語( 目的格 )
を挟むため「 誰々をがっかりさせる 」。
「 がっかり 」な点は共通する。
–
◆ 上掲の国語辞典が示すように、 カタカナ 「 ダウン 」 は、
ネガティブ一辺倒に近い。
一方、 英語 ” down ” は、 印象のよい 「 落ち着く 」 や
「 書き留める 」 意味にも使う。
- settle down ( 落ち着く、 身を固める )
※ 句自動詞・句他動詞
– - calm down ( 落ち着く )
※ 句自動詞・句他動詞
– - cool down ( 冷静になる、 鎮まる )
※ 句自動詞・句他動詞
– - write down ( 書き留める )
※ 句他動詞
– - jot down ( ささっと書き留める )
※ 句他動詞
–
句動詞の ” down ” は、副詞が目立つ。
” let somebody down ” でも副詞。
◆ 神経作用を 落ち着かせる 鎮静薬の俗称は、 ” downer “。
【発音】 dáunər / ˈʌp.ɚ
【音節】 down-er (2音節)
対する ” upper ” は、 神経を興奮させる「 覚醒剤 」。
【発音】 ʌ́pər
【音節】 up-per (2音節)
複数形 ” downers “、 ” uppers ” で使われるのが一般的。
複数語尾 ” s ” を添えるのが通例ということ。
–
他動詞 ” down “( おろす ) と ” up “( 上げる ) に、
「 ~ するもの 」 を意味する接尾辞 ” er ” を加えて、
それぞれ名詞にしたもの。
【参照】 ” er ” ( ~ する人間 ) の英単語一覧 ( 10語以上 )
–
主な ” downers ” は、「 バルビツレート 」( barbiturate )。
主な ” uppers ” は、「 アンフェタミン 」( amphetamine )。
違法薬物扱いの ” uppers ” は、洋画にもよく出てくる。
–
◆ ” down ” を押さえた後は、” let ” に話頭を転ずる。
【発音】 lét (1音節)
「レッツゴー」( Let’s go )の ” let “。
これまた、日本人にとって親しみがある単語と言いたいところ。
けれども、「 ダウン 」と異なり、中身は知られていない感がある。
” let ” は、「 使役動詞 」( causative verb )のひとつ。
人やものに「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」を表す動詞である。
–
使役動詞として、教科書で紹介される3つがこちら。
- let
- make
- have
さらに、英文法上は使役動詞ではない ものの、「 to 不定詞 」
を伴うと、同然の機能を有するようになるのが、
- get
“I got my son to look after the dog.”
(息子にその犬の世話をさせた。)
(息子にその犬の世話をしてもらった。)
こんな風に、” get ” が「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」を表すことは、
中級学習者であれば、難なく理解できるはず。
使役動詞としての ” let “、” make “、” have “、” get ” は、他動詞。
- 他動詞とは、主語以外の人やものに影響を及ぼ動作
- 自動詞とは、目的語がなくても、意味が完結する自己完結の動作
人やものに 「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」のが使役動詞なので、
当然、他動詞になる。
–
【参考】 ※ 外部サイト
–
◆ 4語の使い分けの原則をざっくりまとめる。
- let ( 許可を「 与える 」) → 主に目上が使うので強気
- make ( 無理やり「 させる 」) → 多くが強制的で強気
- have ( 当たり前のことをしてもらう ) → ごく自然で中立的
- get ( 説得してやってもらう ) → お願いしつつ中立的
『 英語ライティングルールブック 第3版 』 によると、
” let “、 ” make “、 ” have ” の3語のうち、
「 上下関係や強制のニュアンスがなく、
最も幅広い状況で使えるのが have 」
とある。
–
▲ 本書は、 日本語ネイティブ向けの英作文の参考書として 定評がある。
–[ 初 版 ] 2004年発行
–[ 第2版 ] 2011年発行
–[ 第3版 ] 2019年発行
–
全部読んできたが、 丁寧に改訂を重ねてきている。
おすすめ。
◆ 米国発の名高い ” writing style books ” は、
法律文書のが定番は、
いずれも、 引用形式 ( citations ) としても活用される。
社内記者用に作成された「 APスタイルブック 」は、
1953年に一般向けに発行された。
各社で説が分かれる分野も少なくない。
どれを採用するかは、使用者( 雇用主 )や発注者側の指定に
よりけりだったりする。
–
この他にも、 歴史と版を重ねた有名どころが 複数存在 する。
–
そのため、 先ほどご紹介したセイン氏のDHC版も含め、
どのスタイルブックも 「 絶対視 」 はしない方がよい
と私は考える。–
–
◆ 日本では、 以下5冊が有力視されている。
- 朝日新聞 『 用語の手引 』
- 共同通信社 『 記者ハンドブック 』
- 時事通信社 『 用字用語ブック 』
- 講談社 『 日本語の正しい表記と用語の辞典 』
- 第一法規 『 用字用語 新表記辞典 』
【参考】 ※ 外部サイト
◆ これまで学んだことを、3大学習英英辞典( EFL辞典 )で確認してみよう。
代名詞が無生物の ” let something down ” の語釈は除外した。
表題の趣旨に合わせて、 ” somebody ” に絞るためである。
” let somebody down “
” let down somebody “
phrasal verb
1. to not do something that someone trusts or expects you to do.
( LDOCE6、ロングマン )
–
” let somebody down “
phrasal verb
to fail to help or support somebody as they had hoped or expected.
( OALD9、オックスフォード )
–
” let sb down “
phrasal verb
to disappoint someone by failing to do what you agreed to do or
were expected to do.
( CALD4、ケンブリッジ )
※ ” sb ” = ” somebody ”
–
◆ 先述の通り、項目立てに ” someone ” はなく、
軒並み ” somebody ” を起用。–
2語の微妙な違いについても、 既に記した。
枠内の ” LDOCE6 ” によれば、 目的語( 目的格 )を後付けにして、
” let down somebody ” とすることが可能。
–
片や、” OALD9 ” と ” CALD4 ” は明記していない。
本稿で取り上げた意味合いであれは、目的格を中間に置く方が普通。
–
とはいえ、文面においては不自然でもない。
- “X let down her fans.”
( X は彼女のファンを失望させた。)
– - “England let down their fans in World Cup defeat to Wales.”
(イングランドはワールドカップでウェールズに負けて、
ファンを失望させた。)
– - “These YouTubers Let Down Their Fans”
(ファンをがっかりさせたユーチューバーたち)
もっとも、「失望させる」ではなく、「 辱める 」 「 威信を傷つける 」
の意味であれば、後付けは一般的にみられる。
- “Lazy students let down Japan’s colleges.”
(怠慢な学生たちが日本の大学の威信を傷つけている。)
日常的に多用されるとは言い難い用法であり、本稿では触れなかった。–
–
◆ 自己使用には、次の基礎パターンを覚えておくとよい。
- “I won’t let you down.”
(私はあなたを失望させません。)
(きっと期待に応えてみせます。)
– - “Don’t let me down.”
(私をがっかりさせないで。)
– - “I’m sorry to let you down.”
(がっかりさせてごめんなさい。)
– - “I don’t want to let you down.”
(あなたを失望させたくないです。)
– - “I didn’t want to let you down.”
(あなたを失望させたくなかった。)
– - “I never wanted to let you down.”
(あなたを絶対に失望させたくなかったのです。)
–
【関連表現】
” I won’t disappoint you. ”
https://mickeyweb.info/archives/2636
( きっと期待に応えてみせます。)
【参考記事】 ※ 外部サイト
Prince Charles ‘Feels Enormously Let Down’
by Meghan Markle andPrince Harry’s Racism Claims,
Says Source
https://people.com/royals/prince-charles-let-down-racism-claims-meghan-harry-oprah-interview/
2021年3月18日付
【参考動画】 ※ YouTube
▼ 英語のみ ( 全長 1分33秒 )
Judge Greets Classmate Leaving Jail After Recognizing Him in Court
https://www.youtube.com/watch?v=ILWz8_x9SN4
( 法廷で同級生に再会した裁判官 )
動画開始後 1:15 で、裁判官が力強く声かける。
– “ Don’t let us down. ”
– ” I won’t. I promise not to. ”
そっぽを向きながら愛想なく応え、 さらりと冷たく流した面持ちが
映し出されているが、 実際は気恥ずかしく、 照れていたのかも。
–
▼ 日本語字幕付き ( 全長 3分31秒 )
同じ中学校を卒業した二人の優秀な生徒、社会人になって「法廷で再会」
https://www.youtube.com/watch?v=USQKcikyGJ0
裁判官の声かけは、 動画開始後 3:18