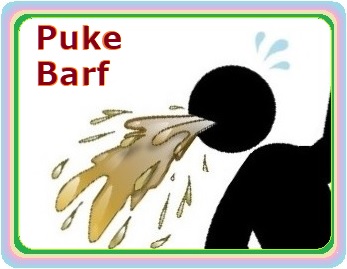This is not the case.
2026/01/01
(1) これは該当しない、 そうではない、 そのことではない
(2) これは事実ではない
–
直訳は 「 これは、そのケースではない 」。
とにかく、 確信を持って、
「 そうではない 」
–
と言いたい。
【 趣旨 】
内容を 真っ向から 否定したい
◇ 「 そのケース 」に該当しない–
◇ これは 「 無関係 」 「 違う 」
–
こう結論づけている。
口語使用が目立つ印象だが、 文面でも使える。
–
◆ 主な意味は2つ。
(1) これは該当しない、 そうではない、 そのことではない
(2) これは事実ではない
どちらかの場合も、両方使える場合もあるので、 文脈で判断する。
和訳として、 「 これは 」 の代わりに 「 それは 」 でもよいだろう。
この2つも日頃より見聞きする。
- That is not the case.
- That’s not the case. ( 後述 )
指示代名詞 ” this ” と ” that ” は、 日常的には、
そう厳密に区別されていない模様である。
過去形 ( past tense ) は、
- That was not the case.
- That wasn’t the case.
- That’s not the case. ( 先述 )
【 注 】 ” that’s ” は、 以下いずれかの短縮形。
” that is “、 ” that was “、 ” that has ”
–
◆ –ポイントは ” case “。
【発音】 kéis (1音節)
名詞のみの単語で、 かなり多義。
可算名詞と不可算名詞を兼ねる。
英単語全体における位置づけは、 最高レベル。
すなわち、 最頻出かつ最重要の英単語。
- 重要度:最上位 <トップ3000語以内>
- 書き言葉の頻出度:最上位 <トップ1000語以内>
- 話し言葉の頻出度:最上位 <トップ1000語以内>
–
◆ 名詞 ” case ” の基本的意味は、 日本でも多用されている感がある。
- 場合
- 事例
- 真実
- 真相
- 状態
- 訴訟
- 事件
- 該当者
こちらでもお馴染み。
- ケーススタディ
( 事例研究 )
– - ケース バイ ケース
( 一件一件 )
→ 一律ではなく、 場合 場合 に応じて個別対応
上記はいずれも可算名詞なので、 不定冠詞 ” a ” が基本。
多義とはいえ、 どうにか語源から連想可能な意味合いが大半。
「 落下 」 → 「 落ちてくるもの 」 → 「 降って( 沸く )」
–
どことなく、 トラブルの気配や厄介な雰囲気を帯びる。–
–
【ご注意】
「 容器 」の ” case ” は、 完全に別物。
発音・音節は同じ。
– 語源は、 ラテン語 「 箱 」 ( capsa )
– 原義は、「 握る 」「 つかむ 」
– 可算名詞中心だが、 他動詞 「 箱に入れる 」 もある
【発音】 kéis (1音節)
–
–
◆ ” This is not the case. ” の ” case ” は、
上記の基本的意味をそのまま適用。
–
(1) これは該当しない
そうではない、そのことではない
–
” case ” = 事例、 場合
< 直訳 >
・ これはその事例ではない
・ これはその場合ではない
–
(2) これは事実ではない–
–
” case ” = 事実、 真相
< 直訳 >
・ これは事実ではない
・ これは真相ではない
–
既記のように、 これらの意味の ” case ” は可算名詞のため、
冠詞は不定冠詞 ” a ” が原則。
けれども、 この用法では、 定冠詞 “ the ” となる。
理由は次の通り。
(1) これは該当しない、 そうではない、 そのことではない
→ その 事例、 その 場合 = 特定 の対象を指す
(2) これは事実ではない
→ 「 事実 」「 真実 」は、 本質的に 1つ だけ存在する
–
◆ ” This is not the case. ” は、副詞 ” not ” を用いて、
その 内容を強く否定する。
–
「 違います!」と 言い切る勢い–
–
よって、根拠を示す 自信がない限り、やたらと使う文言ではない。
否定は簡単にできる。
だが、 求めに応じて、 その理由や対案を論理的に
提示できなければ、 信用は得られにくいのが現実。
- “No, this is not the case.”
(いいえ、そうでありません。)
(いいえ、これは事実でありません。)
– - “This is not the case in the US.”
(米国では、そうでないです。)
(米国では、事実でないです。)
(米国には、当てはまりません。)
– - “I guess this is not the case.”
(どうやら、そうでないようです。)
(どうやら、事実でないみたいです。)
※ ” guess ” → 他動詞・自動詞・名詞 「 推測( する )」
– - “If this is not the case here, then I have to think again.”
(もしそうでないなら、自分の考えを改めなければ。)
(もし事実でないなら、自分の考えを改めなければ。)
– - “My experience tells me this is not the case.”
(私の経験上、これは該当しません。)
(私の経験上、これは事実ではありません。)
– - “100% not the case.”
(100% ありえない。)
(それは100%ない。)
– - “That is not the case anymore.”
- “That is no longer the case.”
(もはや、そうではない。)
(もはや、それは該当しない。)
– - “That is not the case yet.”
(まだ、そうではない。)
(まだ、それは適用されていない。)
–
–
–
◆ 逆に、譲歩する際、
これまでの否定の副詞 ” not ” に代わって出てくるのが、
「 仮定・条件 」 の従属接続詞 ” if ”( もしも ~ なら )。
- If that is the case –
- If that’s the case –
- If this is the case –
仮定・条件 「 もしも、その内容通りである なら 」 の意。
(1)
もしも、 これに該当するなら ~
もしも、 そうであるなら ~
もしも、 そのことであるなら ~
–
(2)
もしも、 これが事実であるなら ~
–
しかし、 あくまでも 「 仮定・条件 」 の If。
「 If 関数 」の ” If ” ( 条件指定 ) と重なる機能。
仮定の話では、 力説できず、 説得力もない。
–
表題 ” This is not the case. ” にみなぎる、
「 違います!」と 言い切る勢い–
–
こうした迫力には欠ける。
それもあってか、 さほど見聞きしない、 地味な言い回しの印象。
◆ 真っ向から、 確信を持って否定するのではなく、
やんわりと疑念を挟みつつ 推量 する には、
助動詞 ( auxiliary verb ) の ” would ” を用いて、
- That would not be the case.
- きっとそうならないだろう。
- おそらくそれはないだろう。
使用場面は、 仲間が楽観的な見通しを話した時に、
自分としては、「 それはないね 」 と感じる時。
このまま仲間に述べても、 反発されにくいはず。
会話の流れとして、 この用法の ” would ” であれば、
主張を和らげる 婉曲 ・丁寧 の ” would “ も兼ねる。
–
語気・抑揚に配慮しながら、 ゆっくり穏やかに語れば、
「 まずそれはないでしょう 」 くらいに聞こえる。
「 おそらく ~ でしょうか 」 と物腰が柔らかい。
嫌味・皮肉なしの低姿勢で品よく行儀よく、利便性が高い。
公私不問で応用が利くため、 ぜひとも押さえておきたい。
–
◆ 以下と同じ機能の 婉曲 ・丁寧 ” would ” である。
- I would say – .
- I’d say – . ( 縮約形 )
断定を回避しつつ、 自らの考えをはっきり述べる際に便利。–
- I wouldn’t argue with that.
( それに反論はいたしません。)
( それに異論はございません。)
( 私なら反論はしませんね。)
– - I wouldn’t want you here.
( ここにいてほしくないね。)
( 君に来てもらいたくない。)
( 君に入社してほしくない。)
–
◆ 助動詞 ” would ” の作用は、 非常に多くて悩ましい。
LDOCE6( ロングマン )の指標によれば、
- 重要度:最上位 <トップ3000語以内>
- 書き言葉の頻出度:最上位 <トップ1000語以内>
- 話し言葉の頻出度:最上位 <トップ1000語以内>
【発音】 wəd (1音節)
英単語全体における立ち位置が、 最高水準の ” would “。
” case ” と同等ランク。
駆使できないと、 英語は使いこなせないと言うに等しいほどの
最重要単語なのだが、 扱いにくさは ” case ” の比ではない。
日本語との共通点が多い、 名詞 ” case ” とは段違いの複雑さ。
–
◆ 語源は、 古英語 ” wolde “。
–
古英語 ” wyllan ” ( ~ しようと欲する ) の過去形である。
–
ドイツ語 ” wollen ” ( したい )、 ラテン語 ” velle ” ( 望む )
と同源。
- I would take my annual leave on my terms.
( 年次休暇は自分の都合で取ります。)
– - I would take control of my career.
( 自分のキャリアは自分でコントロールします。)
一応謙虚さを伴うものの、 きっぱり断言する意思を放つ口調。
–
◆ 丁寧の真逆に近い、 いらだちの ” would “ も頻出。
- Why would she do that ?
( そんなこと、彼女がやるかよ。 )
( なんで彼女がそんなことするんだ。)
– - Why would she say that ?
( そんなこと、彼女が言うかよ。 )
( なんで彼女がそんなこと言うんだ。)
–
どんな辞書を調べても、 語義がずらりと居並ぶ ” would “。
頭で理解するのは、 大したことない気もするが、
本当に分かるようになるまでは、 実に大変。
「 最難関の助動詞 」 と私は受け止めている。
「 最難関の英単語 」 のひとつかもしれない。
日本人学習者にとって、 それほど難しいと思い至る。
” would ” は、 複雑多岐を極める含みが多すぎる。
母語にないタイプで、 イメージしずらく、 把握困難。
だから、 口に出して、 書き出して、 実際に使ってみて、
恥をかきつつ学びました。
–
【参考】 ※ 外部サイト
- 「 Would 」 の活用法 ( 総まとめ )
https://hapaeikaiwa.com/blog/2017/03/23/%e3%80%8cwould%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%ef%bc%88%e7%b7%8f%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bc%89/
2017年3月23日付
◆ 使ったことのない ” would ” を見聞きしたら、
その文脈を丸ごと即日 「 単語帳 」 に加える習わし。
そして、 すぐさま真似して、 しれっと自分で使ってしまう。
語学の基本は 「 真似 」 だから、 幼児のように無邪気に真似る。
昨日学んだばかりでも、 今日のメールに忍び込ませたりする。
–
日常に即刻ぶち込む
–
せっかく学んだ表現、 高揚感が冷める前に、 ちゃっかりと起用。
使い道を作り出し、 速やかに実行して、 一気に脳に焼き付ける。
こうすれば、 自律性・能動性を保ちながら、 ずんずん学習が進む。
どんどん使ってやれば、 新入りも喜び、 ちゃんと定着してくれる。
日常にそんな機会はない ?
そう、 だから英語ができない。
ぶち込む機会が平素になければ、 オンライン英会話などで作り出す。
「 ネイティブキャンプ 」 及び 「 レアジョブ 」 を推す。
【 景品表示法に基づく明示事項 】 ↑↑
ご両社とも、アフィリエイトのリンクではありません。
対価 ( 紹介料 ) は一切いただいておりません。
記事の右端と下部の広告欄は、アフィリエイトです。
( 2026年1月 現在 )
趣味を含むライフスタイルを、 可能な範囲で2か国語環境に改造する。
「 英語でなんて言うんだ 」 と調べ、 好きな領域をバイリンガルに。
機会ゼロだと便便だらり身につかず、 英語を運用できるようにならない。
–
–
支離滅裂で滅茶苦茶な流れは印象深く、 記銘 → 保持 → 想起 が円滑。牽強付会のストーリーは記憶に残りやすいので、 奇妙奇天烈な例文を作り、
上司・同僚・家族・ペットを巻き込み、 勝手にこじつけ、 脳に刷り込む。
–” What’s the use of – ? “ より ← 実例紹介
–
【参照】 「 Gmail 」 で作る単語帳 ← 実例紹介
–
長年こうした努力を積み重ねても、 次々新鮮な用法が出てくる
ため、 ” would ” は一貫して 「 最難関の英単語 」 なのです。
夜昼お構いなく、 助動詞 ” would ” には過敏になっている有様。
英語ネイティブが気軽に取り出す姿を見ると、 うらやましくなる。
悔しいわ。
–
【参照】 ” Will you marry me ? ” は、 怖すぎる求婚か
◆ 以下、 ” No need. ” より再掲。
「 英文法 」 と 「 英単語 」 の自習に時間をかけすぎてはならない。
文法・単語などを自習しすぎると、 時間切れになる
拙い自己満足に堕し、 報われない努力になりがち。
自己満足の英語学習に酔い、 伝わる英語は縁遠くなる。
( 中略 )
自分の英語学習・職務経験を踏まえて結論すると、
ばんばん使ってみないことには、すとんと腑に
落ちる具合に知識も意識も赴かないのが、 外語としての英語。
–
常日頃、 やり繰りして、 英語を使う機会を作っていない 人が、
教材中心に学び、 まともに理解できているとは、 到底思えない。
–
残酷な話だが、 「 勘違い 」 と 「 自己満足 」 で終わっている
可能性が高いと思う。
それゆえ、 くどくどしく不羈奔放な筆致で喚起を図ってきた。
自力で英文を書いていますか ?
ご自分の口を動かし、 発声していますか ?
テキストと問題集をやりすぎていませんか ?
うろうろ当惑している訪日客に声掛けできますか ?
もっとも、 「 できたつもり 」 「 できるつもり 」 の英語で
納得できるならば、 それはそれで学習の形を成すかもしれない。
–
▲▲ 再掲終わり ▲▲
自分で使わないと、 英語はできるようにならないと思います。
もったいないので、 しまい込まずに、 使ってあげましょう。
【類似表現】
” That’s a different story. ”
https://mickeyweb.info/archives/15229
( それは話が違う。)
–
笑われたり、 バカにされたり、 差別を受けることも語学修行の一環。
傷つくことを変に避けてしまうと、 身につけがたくなる気がする。
異質な対象を疎むのは、 人間の摂理 ( human nature ) と考える。
同類を好む人間の本能で、 縄張りにずかずか踏み込まれるのを嫌がる。
「 外人 」 という言葉を陰で使い続ける日本人は少なからず存在する。
( 中略 )
–
–
外語学習の本質は、 異文化に立ち入ることだから、 傷つく場面も多い。英学徒たる者、 皆が通る道だと覚悟すべし。
( 中略 )
50年以上、 もう散々な目に遭っているがなんのその、 まあ慣れます。
冷たくあしらわれる都度、「 はいはい、 また出たわ ♪ 」 と意に介さず。
何食わぬ顔でかわし、 てんで取り合わないので、 今は余裕です。
堅忍不抜というより、 「 いじめられて一人前 」 と肝っ玉を据えている。
「 職務・給与・報酬の一部 」 と、 虚心坦懐にさらりと受け入れている。
悔しさに涙があふれても、 行き着く先は、 私の養分、 成長の肥やし。
がつんと打ちのめされ、 打ちひしがれた涙の思い出は忘れない。
嫌な思いをした分、 びっくりするほど銘記しやすく、 効果抜群。
長期記憶 ( long-term memory ) に直行する、 段違いの力。
直接体験 ( firsthand ) なので、 忘れにくいに決まっている。
なんか癪に障るが、 おかげ様で長期記憶化して学び取れました。
死ぬほど 恥かかないと !!
–” No need. “ より
–
–
–
誰かに話したくなる人生で役立つ雑学まとめ
https://www.youtube.com/watch?v=vcAoowDs6_k&t=603s
2024年10月6日付 ※ 動画全長 12分58秒
–
–
英語がうまい方が自信がありそうかといえばそうでもなく、 英語を使いこなそうと果敢に立ち向かう人が自信を強める傾向が見受けられる。
失態・落胆・侮辱・赤っ恥の一切合切が、 血となり肉となり糧となる。
大恥かくほど克明に覚えられて、 ” No pain, no gain. ” を地で行く。
外語を常時使って働く者ならば、 実体験から分かり切った道理である。
汚辱と恥辱にまみれ、 面子を失い、 懲りずに日英を学び続けて半世紀。
使ってみることがいかに有意義か知り尽すので、 がみがみ言い立てる。
–
” conclusive “ より
–
◆ おすすめ YouTuber ( 下記 ) と学習上の着眼点は、 ” No need. ” に詳述した。
( 図入り )
—
–
さしあたり、
発音記号や音節を考えずに、 興味本位でじっと眺めてみる。
画面を戻して、 とことん観察 ( rewind and rewatch )。
必要に応じて、 コマ送りにする。
–
▼ TH
▼ F
–
▼ L
–
▲ 焼肉しゃぶっているよう–
日本語を話す時、 このようになりますか。
一瞬たりともないと思います。
なぜなら、 日本語の発音には不用な動きだからです。
日英の音は、 舌・唇・歯・呼吸間の相互作用が
まったく違います
–日本語音と同じ感覚で英語音を発音するから伝わらない。
–
👄 唇をよく見て 🫦
–リスニングばかりで口は置いてきぼりの日本人が多すぎ。
–英 語 「 息の音 」
日本語 「 声の音 」–
–
実際に声を出してみないと、 英語の発音はできるようにならないです。
日本語とは完全異質だから、 耳で聞くだけでは、 口から出てこない。
どんなにリスニングをしても、 自ら発声しない限り、
いつまでも話せない。
ごく自然に習得できるよう
「 人間の本能 」 に組み込まれた
第一言語 ( 母語 ) と違う点
根底からして異質な言語がお安く口から出るって、 結構なホラー話。
映画 「 エクソシスト 」 ( 1973年公開 ) の世界です。
適切な訓練なくして、 現実的にはあり得ないことに気づきましょう。
ご自分のお口–
を 動かしましょう
–
” Joce’s YouTube “ より
–
Joce Bedard—カナダ人女性 ↑ 先述の推しの YouTuber
日本語母語話者にとって、
英語の発音は動物の鳴き声に近い。
日本語で表記しがたいのは言うもおろか。
犬猫の声と一緒で、 そもそも日本語では書き起こし
きれないのに、 英語音を無理くり邦文で表現しようとする。
発音( 音声 )記号と違い、 舌・唇・歯・呼吸の相互作用
を反映していない表記だから、 感覚的理解でどん詰まりに。
日本語音と同じ感覚で英語音を発音するから伝わらない。
等しく不条理だからアプローチを変える。
口周りをまじまじと見据えて、 模倣する。
👄 口をよく見る 🫦
–
※ やり方は、 ” integrity ” へ ( 図入り、 動画入り )
–
【参考】 ※ 外部サイト
- 多言語の習得は 「 音 」 から 脳領域特定、 文法理解早く
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF251YP0V20C24A2000000/
2024年2月26日付–
相性のよさそうな
発信者や番組を見つけて、
がっつり食らいつく。
★ 日本人学習者を主たる顧客と想定した素材は、
長期的にはあまり望ましくないと私は考える。
中級学習者 が潜在能力を引き出し上達するには、
日本人相手ではない番組を中核に据える方が名手。
–
【 主な理由3つ 】
日本語母語話者向けに、 ほどよく加減され、
念入りに作り込まれた印象を受ける番組が多い。
登録者を増やすためか、 販売促進のためか、
どうしても視聴者におもねる調整が欠かせない。
–
理由は3つのデメリット。
(1) 漫然と受動的に視聴しただけで、 会得したと勘違いして、 自己満足に陥りがち
(2) 自分の頭や口を動かさずに時間を使い切り、 成長しそびれているのに気づけない
(3) 手入れ後の日本人受けする英語なので、 そう自然ではない状態の英語が目立つ
–
一般向けの素材に慣れ親しんできた学習者であれば、
割合すぐ見透かせると思う。
–
–
常用語は、無限に無償提供されている。採集素材は、至る所に ある。
本や会話はもちろんのこと、映画、ラジオ、標識。
一般人が気軽に発した生の英語に触れられる穴場は、
YouTubeの コメント や商品 レビュー( アマゾンなど )。教材としても推奨できる。
【参照】 おすすめ YouTuber と着眼点は、” No need ” に詳述
( 図入り、 写真入り、 動画入り )–
お手元に英語素材がなければ、 手始めに コメントとレビュー
から取り掛かるとよい。
–魅了された動画や商品の英文コメントを、 ついでに読む 「 習慣 」。
「 今日からできる 」 英語学習であり、 人生を変える効果がある。
–
翻訳機能を使えば、 その場で答え合わせでき、 気苦労は少なめ。
すこぶる奨励する学習法のひとつであり、 私も毎日実行している。
玉石混交とはいえど、 手近な インプットの宝庫で、 とにかく楽しい。
昔ながらの新聞・雑誌の読者欄は言うまでもない。
なにしろ、 投稿者の感情がほとばしり、 エネルギーが充満する。
「 コメント回り 」 と称して、 めぼしい日英表現を見つけては、
こうして語彙採集するのが、 永年の私の日課である。
見聞きした対象を、その都度、書き留めるだけ。
だから、 ネタ集めに困らない。
なんでもかんでも 「 先生 」 と勝手に思っている。
–
–
「 語彙採集 」 より
◆ 再び ” No need. ” より。
–
日常語すら心許ないのに、 高難度の語に飛びついたところで、 まず使えない。
マニアックなものに手を出す前に、 誰もが使う単語と表現をきっちり固める。
日常会話さえできないのに、 ハイレベルの知識を詰め込んでいるのが日本人。
自ら使うに至らぬまま、 しゃかりきに習い理論武装を重ねる方が極めて多い。
高難度な単語を覚えることに精一杯で、 簡単な単語を使いこなす余裕がない。
会話なくして口を動かさない 「 英語の勉強 」 に満悦し、 時間を使い果たす。
口で発声してみなければ、 絶対しゃべれるようにならないのは争えない事実。
勉学に専念し、 user になることなく、 English learner だけで一生を終える。
おかしな話だ。
認識止まりが learner、 自分で語彙運用 ( command ) を試みるのが user。
▲▲ 再掲終わり ▲▲
正しい文法は尊ぶべきものだけれども、
日英の総合的な雲泥の差を加味すれば、
深入りしすぎる前に切り上げないと、
それだけで人生が終わってしまう。
–
プロであれば、 好き嫌い抜きで、 強行突破する折が多々生じる。お金をいただいており、 正式に職責を負うためで、 言うを俟たない。
対して、 アマチュアの英語学習者の場合、 苦手でしんどい課題に、
あまり時間をかけすぎない方が、 好手ではないかと感じている。強行突破で金稼ぐプロ以上に、 不振に見舞われる危機に立たされる。
–( 中略 )
–非現実的な 「 理想 」 に執着するよりも、 ご機嫌に続ける方が、
最終的に勝ることは、 おびただしい学習者の挫折を見て学べる。最初から欲張らずに、 さして無理なく継続できるペースを保つ。
不得手分野は、 そこそこ自信がついてから、 戻ってくればよい。
一旦棚上げにし、 得意分野をきびきび歩む方が、 ぐんと伸びる。
手つかずでも、 影響がなさそうであれば、 後回しまたは手放す。
辞める・病める人間になる前に、 達成しやすい目標に修正。
自己評価が健全で成熟した勇気のある学習者なら、きっとこうする。
–” no need “ より
–
–
目標が違うプロ・セミプロの基準は別で、 軌を一にするはずないのが常識。同じ野球でも、 「 プロ野球 」 と 「 高校野球 」 を同水準で論じない。
どちらも食うか食われるかの真剣勝負だが、 同じ土俵で向かい合わない。
あるいは、 草野球を楽しむアマチュア選手にプロ野球の厳しさは不相応。
並々ならぬ犠牲を伴うのがプロの道、 無報酬で立ち入るべき世界でない。
こと英語教育に限っては、 久しく混こぜにしてきた異常さに気づくべし。
–” conclusive “ より
–
–
★ 中級の大人であれば、苦手分野には構わず
相性と力量に釣り合う、 得意分野の「 生の英語 」 に絞り、
–日常にぶち込む
「 人生に残された時間 」 との兼ね合いを考慮すると、
苦手分野に近づかない勇気と決断は大切。
英語で稼ぐプロとは違う。
プロは 「 お金をもらう側 」。
予算も設備も人脈も桁違い。
実力と努力量も当然違う。
「 お金を払っている側 」 の中高年であれば、
暮らしが 「 楽しくなる 」 学習法がベター。
得意分野の英語を突破口にする。
手痛い挫折から逃れられ、 ご機嫌に続く。
–「 日本語と英語の違い 」 より
–