Devastated
2023/04/25
打ちひしがれた、 がっかりした
災害時などのニュース報道にも出てくるが、 個人レベルでも
多用する人が少なくない。
つまり、 比較的よく見聞きする形容詞なのだが、 その割に
日本人学習者には縁遠く、 カタカナになる気配もない。
【発音】 dɛ́vəstèɪtəd
【音節】 dev-as-tat-ed (4音節)
意味と字面が何となく似ている形容詞 ” desperate ”
( 絶望的な )が、 「 デスパレート 」 としてお目見えする
機会が増えているのと対称的。
【発音】 déspərət
【音節】 des-per-ate (3音節)
「 デスパレット 」などと聞こえる
” devastated ” の 「 打ちひしがれた 」 「 打ちのめされた 」
との定訳から考えると、 若干大げさな印象がある。
個人がしょっちゅう使うには、 重たすぎる。
–
ていやく【定訳】
最もよいとして評価の定まった翻訳。
決定訳。 標準訳。
( 広辞苑 第七版 )
–
◆ 実際の個人用途では 「 がっかりした 」 「 がっくりした 」
くらいの意味合いで起用されていることが多い。
この2語は、落胆の程度が異なる気もするが、
次の国語辞典では同義扱いされている。
–
「 がっかり 」
副詞
落胆したさま、失望したさまを表す語。
がっくり。
( 精選版 日本国語大辞典 )
” devastated ” は、 動詞 ” devastate ” の過去分詞
” devastated ” が形容詞化したもの。
【例】
”scared”、”undisclosed“、”organi
”disgraced”、”estranged“、”disgruntled”
” devastate ” には、 他動詞と自動詞がある。
※ 他動詞のみとする辞書も多い
– 他動詞 「 荒らす 」 「 打ちのめす 」 「 がっくりさせる 」
– 自動詞 「 くじけさせる 」
” devastate ” の語源は、
ラテン語 「 さらに荒れた状態にする 」( devastatus )。
この語源通り、 ” devastate ” の意味は荒れまくり。
–
” devastate “
1. to completely destroy a place or an area.
2. [often passive] to make somebody feel very shocked and sad.
( オックスフォード、OALD9 )
【発音】 dévəstèit
【音節】 dev-as-tate (3音節)
※ 下線は引用者
–
「 破壊 」 そして 「 非常なショックと悲しみ 」。
下線部が示すように、 極端な度合い であるのがポイント。
これが形容詞となったのが、
–
” devastated “
extremely upset and shocked.
( オックスフォード、 OALD9 )
【発音】 dɛ́vəstèɪtəd
【音節】 dev-as-tat-ed (4音節)
※ 下線は引用者
その結果、先述のように「打ちひしがれた」
「打ちのめされた」が定番の和訳となる。
うちひしぐ【打ち拉ぐ】
1. 強い力で相手を打ち砕く。戦いで相手を壊滅させる。
2. ( 多く受身の形で )強い衝撃で意気・意欲を完全になくす。
–
うちのめす【打ちのめす】
はげしくたたいて、相手が起き上がれないようにする。
転じて、( 心・身に ) ひどい 打撃を与える。
( 広辞苑 第七版 )
※ 下線は引用者
–
上掲 ” OALD9 ” と広辞苑を比べると、意味はかなり重なる。
緑字の ” passive ” と 「 受身 」 まで一緒。
よって、 2語は定訳として的確と考えられる。
大被害を伴う災害時には、 確かに役立つ和訳である。
-たし
◆ ところが、この定訳を個人の日常で生じる、ちょっとした
トラブルで使うと、 一転しておかしく聞こえがち。
大げさな物言いは、 社会人としては望ましくない。
そのためか、 個人的立場で使わない人もいる。
きっと ” OALD9 ” の語釈通りの解釈をしているのだろう。
その反面、 常用する人々が珍しくない点にも触れた。
必ずしも、 仰山な言い振りが好きなのではない。
主に 「 がっかり 」 「 がっくり 」 の意味でとらえている人たちである。
–
–
I was devastated.
–
こんな感じで使う。
時に、ため息混じり。
日頃、筆舌不問で接する機会は珍しくない。
さて、これをどう訳すか。
定訳だとこうなる。
–
–
私は打ちひしがれた。私は打ちのめされた。
もし、 同僚が日本語でこんな言葉を吐いたら、
一体何ごとか、 と驚いてしまう。
どちらも非日常的であり、 日常に親しまない。
御大層な表現であり、 気軽に使えるものではない。
こんな言い回しを私事に用いること自体、 はばかれる。
ナルシスティックな雰囲気が漂い、 なんだか不愉快。
あたかも 『 走れメロス 』 的な自己陶酔が匂い立つ気がする。
–
◆ 本稿で ” devastated ” を取り上げた理由のひとつは、
定訳をそのまま使用すると、 不自然な印象を帯びる単語
の一例を示すこと。
以下にも、 同じ問題が見られる。
” devastated ” の場合、 英語並みに乱用すると、
信用を落としかねないほど、 不似合いなこともある。
それでも定訳と目されるのは、 先ほど比較検討したように、
文法・内容の両条件を満たすから。
この辺が語学の難しさ。
条件に適合しても、 その場面にぴたり合うとは限らない。
” I was devastated. ” とわめく中学生の発言を、
「 私は打ちひしがれたんだ 」 と和訳したとする。
これでは違和感を覚えるに違いない。
誤訳でないにせよ、 適訳でもない のである。
「 僕は途方に暮れたんだ 」 はベターだが、 中学生なら
「 僕はがっかりしたんだ 」 「 ショックを受けたんだ 」
くらいが自然だろう。
–
◆ 真っ当なプロ翻訳者は、定訳を鵜呑みにすることなく、
あらゆる角度から再検討する習慣をもつ。
普段から 類語辞典やコロケーション辞典 を駆使し、
自然で分かりやすい表現を執拗に追求する。
言葉は生き物なので、 時代の変化を追う好奇心も必要。
概ね地味な作業だが、 どんぴしゃりの訳を当てた時は、
我が意を得たりだ。
–
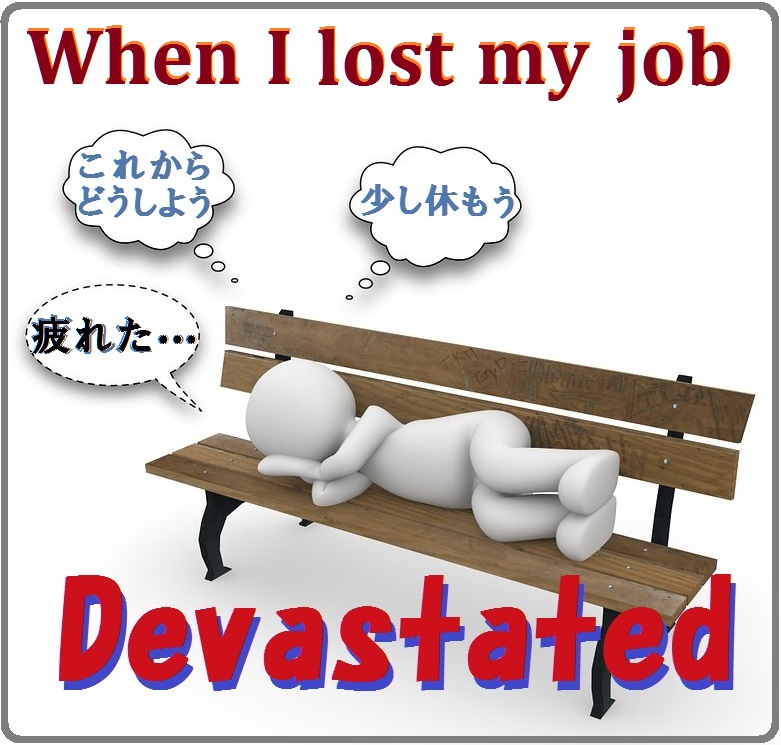
–
忘れがたき経験
- “I felt devastated when I lost my job.”
(失職した時、私は途方に暮れた。)
ー - “He was devastated by her passing.”
- “He was devastated by her death.”
(彼は彼女の死に打ちのめされた。)
ー - “I was devastated to hear the news of Mr. X’s passing. ”
“I was devastated to hear the news of Mr.X’s death.”
(X氏の訃に接し、打ちのめされた。)
ー - “I was entirely heartbroken and beyond devastated.”
(もう胸が張り裂けそうで、完全に打ちのめされていた。)
ー - “The church had been devastated by fire.”
(その教会は火災で破壊された。)
ー - “The area was devastated by the earthquake.”
(その地域は地震で壊滅した。)
ー
- “The country has been devastated by war.”
(その国は戦争で荒廃した。)
ー - “Devastated family gathered to say goodbye.”
(別れを告げるため、悲嘆の家族が集まった。)
ー - “We are completely devastated by the loss of my son.”
(息子を失い、私たちは完全に打ちのめされました。)
ー - “I’m also devastated for the families who lost their loved ones.”
(愛する家族を失った皆様のためにも、悲嘆しています。)
ー - “Her parents were devastated over their daughter’s decision.”
(娘さんの決断にご両親は打ちのめされていました。)
–
–
【類似表現】
- ” shell-shocked ”
https://mickeyweb.info/archives/13823
( 強烈なショックを受けて )
– - ” doldrums ”
https://mickeyweb.info/archives/27328
( 停滞、 不振、 ふさぎ込み )
– - ” dire ”
https://mickeyweb.info/archives/31503
( ひどい、 不吉な、 悲惨な )