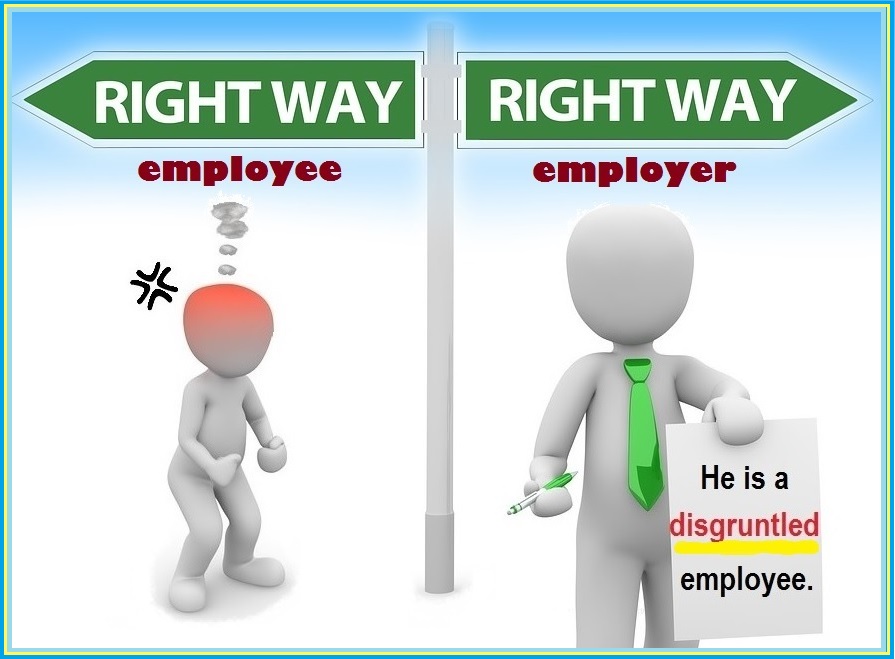Disgruntled
2025/09/23
不満を抱いた
英単語全体から見れば、頻出でも重要でもないが、
特定の場面では欠かせない単語がある。
人事 においては、” disgruntled ” がそのひとつ。
【発音】 disgrʌ́ntld
【音節】 dis-grun-tled (3音節)
日本の学校教育には、ほとんど縁のない形容詞。
だから、ここで取り上げたい。
–
–
disgruntled
annoyed or disappointed, especially because
things have not happened in that way
that you wanted.
( ロングマン、 LDOCE6 )【発音】 disgrʌ́ntld
【音節】 dis-grun-tled (3音節)
–
今風に言えば、 「 ブーたれる 」 様子。
ムッとした 心情と語感が重なる。
–
< 代表格の三者 > 単数・複数
- a disgruntled employee
disgruntled employees
( 不満を抱いた 従業員 )
–
- a disgruntled student
disgruntled students
( 不満を抱いた 学生 )
–
- a disgruntled customer / client
disgruntled customers / clients
( 不満を抱いた 顧客 )
–
◆ “ disgruntled ” は、 形容詞 のみ。
語源は、他動詞 ” disgruntle ” の 過去分詞 ” disgruntled ”
が 形容詞になったもの ( past-participle adjective )。
” disgruntle ” は他動詞のみで、意味は単純。
「 ~ に不満を抱かせる 」 「 ~ を不機嫌にする 」
この過去分詞である ” disgruntled ” が、そのまま形容詞化
したものなので、意味も引き継ぐ。
–
■ 一般的な組織が、
a disgruntled employee
とレッテルを貼って表現する際、
その大半が、
–積もり積もった不満と恨みを抱く従業員を指す。
組織側は「 不満分子 」「 抵抗勢力 」とみなしている
可能性が高い。
–
突発的な日常トラブルならば、話し合いなどで、
さっさと解決にこぎ着けるはず。
さもないと仕事が進まない。
–
長年に渡り不満 が蓄積するのは、
労使双方に不都合 であり、
雇用契約の基本 となる
信頼関係の破綻 を示唆する。
–
一方、学生や顧客については、単発的な問題でも
” disgruntled ” で表したりする。
通常、労使が長期契約に基づく雇用関係であるのに対し、
学生・顧客にはそこまでの縛りがない。
従業員と異なり、学生は期間限定の身分であり、
時間が解決 するため、深刻な怨恨に発展しにくい。
顧客についても、相互に選択の自由が認められている。
「 クレーマー 」( complainer )でもない限り、
長期的な 反目 は回避できる。
◆ 結果的に、” disgruntled” と言えば、” employees “ “。
用法として筆頭に常住するほど、相場が決まっている。
労務不正・情報流出・詐欺・横領・パワハラ を含む組織内
のトラブル事例とその対応策を学ぶと、きっと目にする言葉。
それが ” a disgruntled employee “。
我慢も限界
–
◆ 対応策の主要論調をまとめると、
disgruntled employees–
は、不正の温床
–
まるでスパイ扱い。
内部者がもたらす脅威ゆえ、” insider threats ” に分類される。
まさに「 内なる脅威 」、「 内なる敵 」。
- 「 脅威は内にあり 」( the threat within)
- 「 敵は内にあり 」( the enemy within )
” a disgruntled employee ” とのラベル付けの時点で、
” a potential threat ” に位置づけされていると考えてよいだろう。
なんとも切ない。
–
–
We had to fight the enemy without in the Falklands.
We always have to be aware of the enemy within ,
which is much more difficult to fight and
more dangerous to liberty.( フォークランド諸島問題では、 外敵 と戦わねばならなかった。
自由にとって、はるかに手強く危険な存在である 内なる敵 にこそ、
我々は常に注意しなければならない。 )Margaret Thatcher ( 1925-2013 )
マーガレット・サッチャー 第71代英国首相※ 1984-85年 の鉱山労働者ストライキについて
–
- “Employees are becoming disgruntled about the pay cut.”
(今回の賃金カットで、従業員が不満を抱きつつあります。)
– - “Don’t be disgruntled about such a thing.”
(そんなことで不満になるなよ。)
– - “The upshot is that we have too many
disgruntled employees.”
(結論としては、我が社には不満を抱えた
従業員が多すぎます。)–
–
- “Disgruntled clients were very vocal about
their dissatisfaction.”
(不満を抱いた顧客たちは、自分たちの不平を
たくさん口にしていた。)–
– - “Most of them are unhappy and disgruntled.”
(彼らの大半が不平不満の状態です。)
– - “A disgruntled employee lashed out violently.”
(不満を抱いた従業員が大暴れした。)
– - “I don’t want to deal with disgruntled customers.”
(不満なお客の対応はしたくないです。)
ー - “She was known for her disgruntled look.”
(彼女は不満な顔つきで知られていました。)
– - “We need to do something about disgruntled employees.”
(不満分子をどうにかしないと。)
–
- “The disgruntled employees are pushing for
wage increases.”
(不満を抱いた従業員が賃上げを要求している。)
–
- “She treated me like a dirt so I left feeling disgruntled.”
(彼女は私をゴミ扱いしたので、不満な気持ちになった。)
◆ 既記のように、長期雇用とは 信頼に基づく契約 に他ならない。
敵対意識 ( animosity ) が長く続くのは、 労使双方 にとって好ましくない。
私自身、従業員の立場から、何度か味わってきた苦しみである。
–
【参照】 ” walk out “、 ” 転職とは、一緒に働きたいと思ってもらうこと ”
–
” a disgruntled employee “
のまま、 だらだら 在籍していると、
人生の運を落とす
経験から、こう強く感じている。
今後のためにも、望ましくない。
短期に 乗り切る 方が 救われる
–
すぐさま気づいていただければ、
と私が心の底から思い願うことは、
–
「 雇用のミスマッチ 」は
自己コントロール可能
疲れ切る前に、すばやく動こう。
幸せをつかめる 生き方を選ぼう。
ご自分の人生を、もっと大切に。
–
あせりを解決するためには、自分に適した仕事や環境
–
を見つけることである。そんな仕事や環境はない、とあせっている人は言うかもしれない。
おそらくそんなことはあるまい。
そんな仕事や環境がないのではなく、
そのようなところに行くのを自分の自尊心が妨げているのではないか。
–そこまで感情疲労が激しい のに、
現在の状態にしがみついているのは、
ひとつには現在の状態が自分にある威信を与えてくれている
と錯覚しているからではなかろうか。
–『 もっと素直に生きてみないか 』 p.139.
加藤諦三(著)、 三笠書房、 知的生きかた文庫
1991年刊◇ 引用者により、色・太字・改行は調整済み
勇気を出して
新天地を目指そう
◆ 以下、 ” Test of time ” より再掲。
◆ 自分に適した居場所に身を置く
◆ 自分の勝てる場所で勝負をする
–
この2つが、「 幸せへの近道 」 と私は言い切りたい。
男女不問。
とりわけ、 自分に適した職 に就くべし。
–
よく合う職業に就けば、 自信と自尊心が強化される。
自分の個性に合っているから、 無理なく成長できる。
もともと適性があるから、 すんなり スキル を会得。
稼ぐ力が高まってくると、 生きる力も湧いてくる。
自己肯定感が循環し、 人生の運びがスムーズになる。
ご機嫌に生きられるので、 安定感があり、 信頼される。
結果的に、 自他とも満足して、 健康を維持しやすい。
失職しても、 腕前があるから、 転職には苦労しない。
びくびくせずに生きることができれば、 すがすがしい。
【参照】 toxic relationship、 Please be aware that
–
なにより、 毎日が楽しい。
–
◆ 職業選択の自由を含め、 世界屈指の自由を誇る日本人。
なのに、 適職に縁遠く、 幸せを感じられない人が多すぎる。
こんな気がする。
なぜだろう。
–
–
◆ 転職 しまくった果てに、 思い切って生意気申し上げると …
嫌いな仕事に従事できるほど、 残りの人生 は長くないのです。
Life is way too short for shitty jobs.
いつ終わるか知れぬ我が命、 よくそんな生き方ができるよな。
きっと、 他人には計り知れないご事情があるのでしょう。
でも、 もったいない。
–
【発音】 ʃíṭi
【音節】 shit-ty (2音節)
–
▲▲ 再掲終わり ▲▲
◆ 以下、 ” toxic relationship ” より再掲。
人の言うことを聞き入れるのが苦手な方は、
人の言うことを聞かなければ一向に進まない
ような職業を避けると、 幸せに生きやすい。
–
人間関係が苦手な方は、 人とべたべた関わらなくても
どうにか なりそうな職 と ライフスタイル を志せばよい。
–
自分の 「 素質 」 に見合う職業を慎重に選ぶ。
頭を最大限に使うべき場面。
根本的に合わないのに、 我慢して働くと、 病みます。
▲▲ 再掲終わり ▲▲
【類似表現】
” get worked up ”
https://mickeyweb.info/archives/555
( かっかと興奮する )
“ act out ”
https://mickeyweb.info/archives/9967
( 態度に出す )
“ have an attitude ”
( 反抗的な態度をとる )
“ act up ”
( 身勝手に振る舞う )
日本が無理なら、 海外に行け
–
そのためにも、 英語を身につけておくとよい。
–
–
【参考】 ※ 外部サイト
–
–
https://www.henleyglobal.com/passport-index
2023年4月
海外でダメなら、 戻ってこい。
その頃には、 いくらか潮目が変わっている
Time changes. Every tide turns. Everyone ages.
–
一度、 海外に滞在してみるとよい。
わずか数日間であっても、 心境を含め、 以前と変わるものはある。
–
行く価値は十分ある。
世界は どでかい
万物逃れられないのが 「 時の力 」
No one is immune to the passage of time.
世界屈指の自由を誇る 「 日本人 」。
相対的な信用度も高い。
享受できる権利 を活用すべし。
–
–
https://www.youtube.com/watch?v=9beMtUKgf0Y
2023年11月29日付
( 動画全長 11分49秒 )–
––
https://www.asahi.com/articles/ASS6X2T4XS6XULLI00HM.html
2024年7月1日付
–
アフリカ 「 ナビム砂漠 」 ライブ映像
https://www.youtube.com/live/ydYDqZQpim8
–
–
アフリカ 「 カラハリ砂漠 」 ライブ映像
https://www.youtube.com/live/ME0dPuBtzug
–
–
アフリカ 「 エトーシャ国立公園 」 ライブ映像
https://www.youtube.com/live/AeMUdOPFcXI