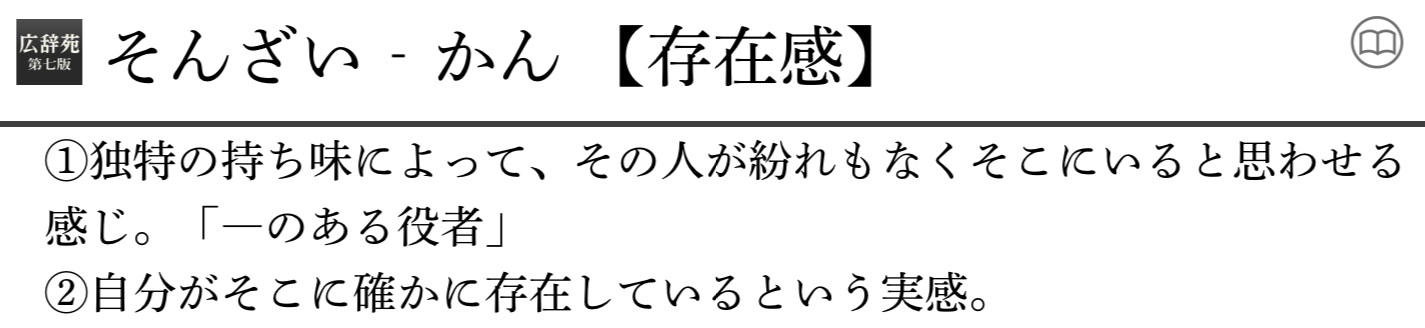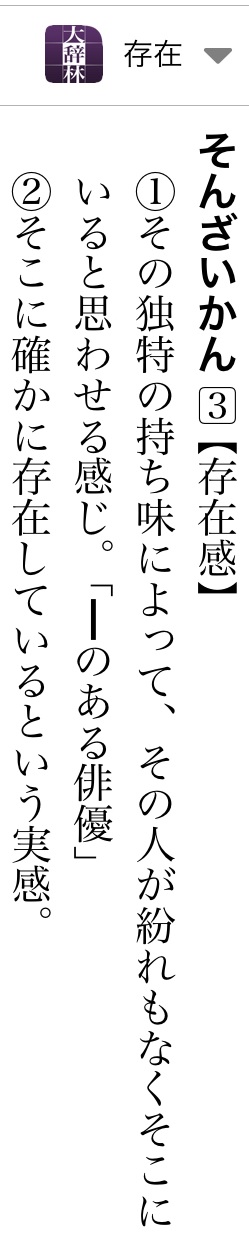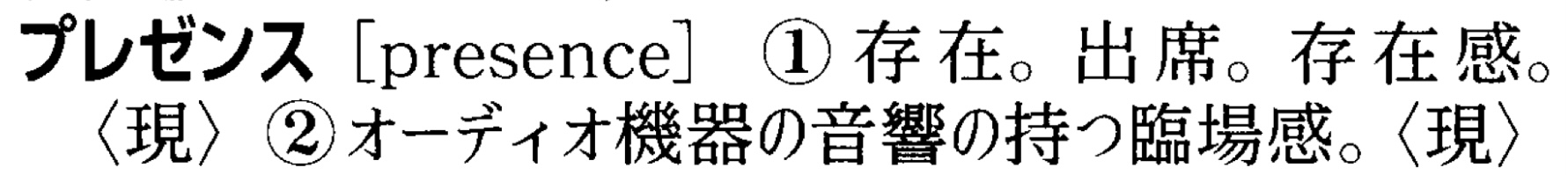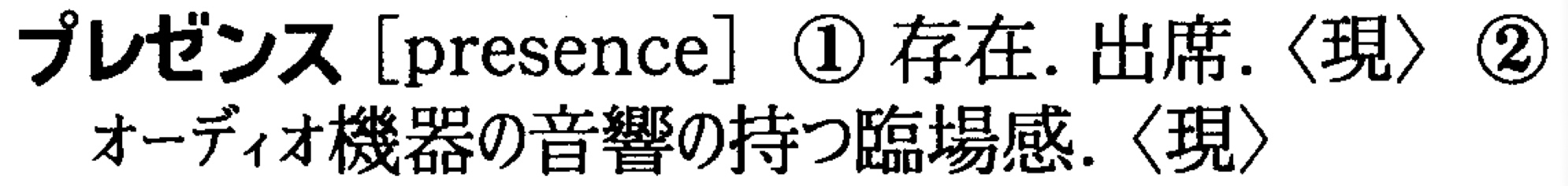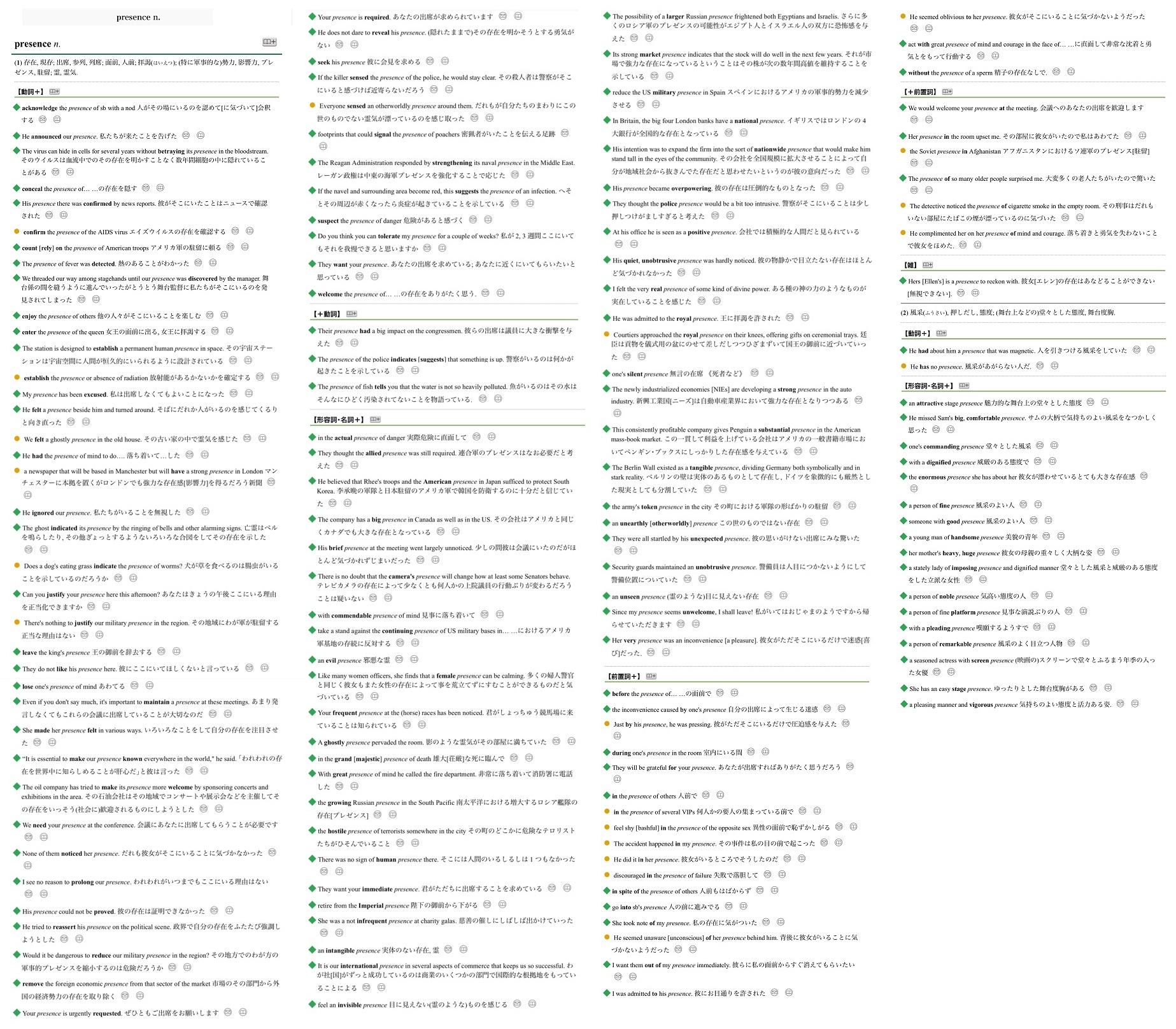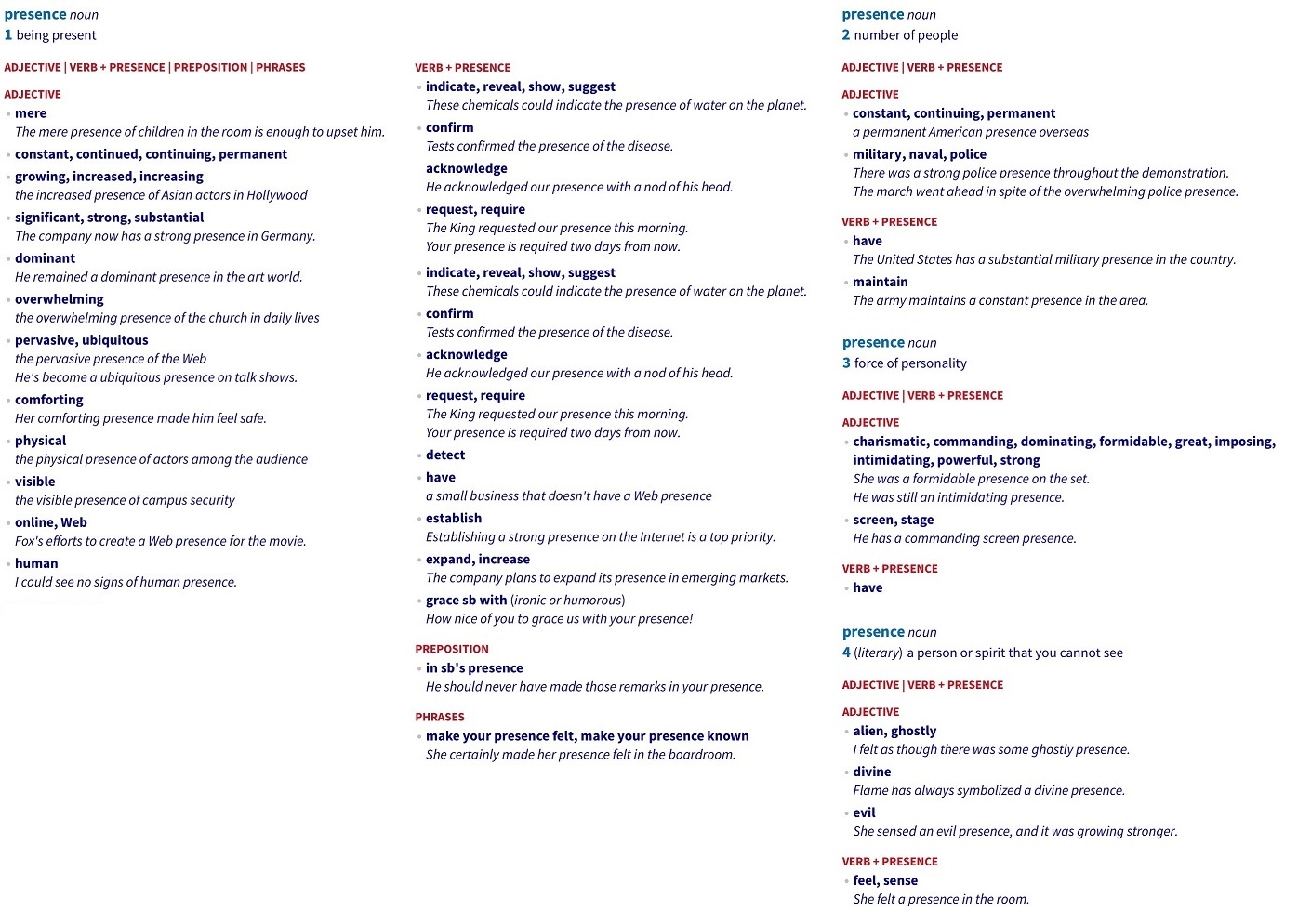Presence
2026/01/23
存在感
「 存在感 」 といったら、 名詞 ” presence “。
定訳である。
【発音】 prézns
【音節】 pres-ence (2音節)
逆に、” presence ” ときたら「 存在感 」に加えて、
次を意味する。
- 存在
- 風采
- 出席
- 面前
- 舞台度胸
- 臨場感
- 駐留
” presence ” は、 やや堅めの言い回し。
英語ネイティブなら、 中学生くらいから自ら使い始めるレベル。
平均的な事務系社会人であれば、日常卑近の名詞である。
さらに、勢力争い に明け暮れる、政治・経済・軍事 の
ニュース報道には欠かせない。
–
◆ 「 存在感 」を冒頭に掲げた理由は、メディアに出てくる
用法で最も目立つ感があるからである。
「 存在感 」さえ覚えておけば、 別の意味の ” presence ” も、
どうにか推測できるはず。
青字で並べたように、 細かく見ると多義。
それでも、複雑多岐ではなく、つながりは見出しやすい。
芋づる式に連想可能な語義中心である。
特定の 「 存在感 」 が 報道価値 を高めるためか、
” presence ” の語意のうち、
最も存在感を示すのが「 存在感 」との印象を抱いている。
( No pun intended. )
そこにいたり、あったりするだけで、 人々の注意を引き寄せ、
話題を提供するため、 メディアに重宝されるのが「 存在感 」。
良くも悪くも強烈な個性が匂い立つ存在には、目も心も、
吸い付けられてしまう。
–
He is still a formidable presence on screen.
( 今でも彼はスクリーンの中で圧倒的な存在感を放つ。)
–
 –
–
–
Powerful screen presence
銀幕における「 存在感 」に視線が釘付け
逆に、 個性のかけらもなく、 似たり寄ったりの様子には、
目をそらしたくもなる。
–
–
–
そんざいかん【存在感】
- 独特の持ち味によって、その人が紛れもなく
そこにいると思わせる感じ。- 自分がそこに確かに存在しているという実感。
–
『 広辞苑 第七版 』
新村 出(編) 岩波書店、 2018年刊
( ロゴヴィスタ アプリ版 )–
- その独特の持ち味によって、その人が紛れもなく
そこにいると思わせる感じ。- そこに確かに存在しているという実感。
–
よくある風潮とはいえど、ここまでの酷似ぶりは珍しい。
–
著名な辞書がこうだと、がっかりしてしまう。
さて、どちらが「 底本 」だろうか。
–
–
–
そのため、” presence ” = 「 存在感 」 が記事中のキーワード扱い
されることもしばしば。
最新の実例をご覧いただくと、きっと手早く理解が深まる。
今年2019年8月~9月に受信した ニュースメルマガ から選んでご案内。
- ” X, provocative presence in civil rights, dies at 91″
( 公民権運動の挑発的存在のXが死去、91歳)
– - ” Build an Online Presence Without Giving Up Privacy”
( プライバシーを保ちつつ、オンライン上の存在感を築く)
– - ” Boost Your Online Presence with Our SEO Services”
( 当社のSEOサービスで、オンライン上の存在感向上)
– - ” Japanese firms seek to boost presence in Africa”
( アフリカにおける存在感を高めようと努める日本企業)
– - ” We live in a world where there is the presence of violence.”
( 我々は暴力が存在する世界に住んでいるのです。)
– - ” X is a Japanese drug giant with a major presence in New York.”
( X社はニューヨークで確固たる存在感を持つ日本の大手製薬会社です。)
– - ” E-commerce has become universal as major retailers
ramp up their online presence.”
( 大手小売店がオンライン上の存在感を強化するにつれ、
eコマースは普遍的なものになった。)
※ eコマース = Electric Commerce、 電子商取引
– - ” President says U.S. will keep a presence in Afghanistan.”
( 米国はアフガニスタンに駐留し続けると大統領が述べる)
– - ” She has been a constant presence at anti-government
demonstrations.”
( 彼女は、反政府デモの常連であった。)
– - ” Researchers point to women’s increased presence
in the workforce.”
( 研究者は、労働人口における女性の増加を挙げる。)
( 研究者は、女性の社会進出を指摘する。)
– - ” His presence was a serious threat to public safety.”
( 彼の存在は公安に対する深刻な脅威であった。)
– - ” I have never lost the sense of God’s presence in my life.”
( 自分の人生で、神様の存在感を失ったことはありません。)
– - ” I was always awestruck by her presence.”
( 彼女の存在感には、常に畏敬の念に打たれていました。)
– - ” His profound presence cannot be replaced.”
( 彼の重厚な存在感は唯一無二のもの。)
– - ” He wants to establish a distinct presence on YouTube.”
( ユーチューブで際立つ存在感を確立することを彼は望んでいる。)
( ユーチューブで際立つ存在になることを彼は望んでいる。)
–
- ” Colombia declared a national emergency after confirming the
presence of the fungus.”
( その菌の存在を確認後、コロンビアは国家非常事態宣言を出した。)
– - ” The first-year assistant coach is making his presence felt.”
( アシスタントコーチ1年目の彼は、自分の存在感を発揮している。)
– - ” X felt her mother’s presence throughout her life.”
( Xは人生を通じて母親の存在を感じた。)
–
- ” Residents did not know of her presence until the reporters
showed up.”
( 記者らが現れるまで、入居者たちは彼女の存在を知らなかった。)
– - ” He said he had 10 weeks left to serve, in the presence of
prison guards.”
( 彼は看守立ち会いのもと、刑期は10週間残っていると述べた。)
–
出るわ出るわ。–
絞り込むのが大変なほど。
上記は、47件から精選した粒ぞろいで、基本的なニュース用法。–
ニュース報道では、 概ねこの2つが中心となる。
–
–
◆ 一般向けの「 カタカナ語辞典 」では、
–
『 コンサイス カタカナ語辞典 第5版 』
三省堂編修所(編集)三省堂、 2020年刊
<三省堂HP>
–
語釈全文である。
この「 第5版 」は、2020年9月10日に発行された。
それから、ちょうど26年前の1994年9月10日に発行
された「 初版 」の全文はこちら。
–
–
『 コンサイス カタカナ語辞典 初版 』
三省堂編修所(編集)三省堂、 1994年刊
–
「 存在感 」 がない。–
だったりするが、意味合いに矛盾はない。
–
ちゅうりゅう【駐留】
- 軍隊が一定期間、ある土地に滞在すること。
( 明鏡国語辞典 第三版 )
–- 軍隊が、外国の土地などにいちじとどまっていること。
( 三省堂国語辞典 第八版 )
–
国防関連は、特に慎重を要するため、次のような
カタカナ表記も近頃は定着しつつある。
–
–
- military presence
( 軍事プレゼンス )
–
- peacetime presence
( 平時プレゼンス )『 新訂・最新軍事用語集 英和対訳 』
金森 國臣(編集)、日外アソシエーツ、2019年刊
無用な誤解を防ぐため、カタカナで書き出しているのであろう。
一般人が用いる用語ではないため、 問題なく通用している模様。
「 プレゼンス 」は、 国語辞典でも項目立てされている。
–
–
プレゼンス【 presence 】
- 存在。存在感。特に、軍事・国家などがある地域へ 駐留・進出
して 軍事的、経済的に影響力 を持つ存在であること。
( 精選版 日本国語大辞典 )
–- 存在。存在感。特に、軍事・国家などがある地域へ 駐留・進出
して 軍事的、経済的に影響力 をもつ存在であること。
( デジタル大辞泉 )
–- 存在すること。特に、国外での 軍事的・経済的影響力 の存在。
( 広辞苑 第七版 )
–- [ 存在の意 ]
国外における 軍事的・経済的影響力。
( 大辞林 第四版 )
- 存在。
- 威力を誇示すること。示威行為。
( 三省堂国語辞典 第八版 )
–
※ 下線・ハイライトは引用者
他国における 「 軍事的・経済的影響力 」 とある。
–
『 精選版 日本国語大辞典 』 と 『 デジタル大辞泉 』 は、
一言一句一致しているのが、 目を引く。
–
▼ 精選版 日本国語大辞典
–
▲ デジタル大辞泉
–
◇ 小学館 『 デジタル大辞泉 』 特設サイト
https://daijisen.jp/digital/index.html–
※ いずれのアプリも、物書堂 版
◆ 物書堂 版アプリの『 デジタル大辞泉 』は、2012年発売の小学館
『 大辞泉 第2版 』の 書籍版 に基づいているが、 その後も継続更新
している小学館データベースの最新データが反映されているため、
書籍版を超える 収録数 を誇る。
一方、2006年刊の『 精選版 』 の本家本元は、日本最大の国語辞典
として名高い、『 日本国語大辞典 第二版( 全13巻+別巻 ) 』
( 2000~2002年刊 )。
通称『 日国 』 ( にっこく )。
念のため、『 日国 』も調べてみたところ、 上記『 精選版 』
と同一の語釈だった。 ( 第11巻、 p.1091. )
両者とも、小学館 が出版する辞書とはいえ、完全一致はいかがなものか。
「 持つ 」 と 「 もつ 」 の使い分けで、 区別したつもりなのか。
デリカシーに欠けた感のある、 清々しい大胆さもなかなかね。
–
- ” Rally against presence of U.S. nuclear aircraft carrier”
( 米原子力 空母のプレゼンス への反対集会)
– - ” Tensions continue to rise over U.S. military presence”
( 米軍のプレゼンスに対する高まり続ける緊張感)
– - ” Governor push for smaller U.S. military presence”
( 米軍のプレゼンスを縮小するよう知事が要請)
–
- ” Resentment over the disproportionately large military presence”
( 軍の大きすぎる存在感に反発)
– - ”
The U.S. military presence has provided security benefits.”
( 米軍の存在は、安全保障面で利益をもたらしてきた。)
–
- ” The military presence, however, is widely unpopular.”
( しかし、軍の存在は大いに嫌われている。)
– - ” The military presence has been cut to somewhere around
1,000 troops now.”
( 駐留する兵員数は、今や1,000名程度まで削減されている。)
–
- ” Many local residents are unhappy about the military presence.”
( 多くの地元住民は、軍の存在に不満を抱いている。)
–
- ” X confirms US troop presence” ※ ニュース見出し
( X国、米軍の駐留認める)
– - ” US completes Afghanistan troop withdrawal
to end 20-year presence”
( 米軍、20年間駐留したアフガニスタン撤収完了)
–
2021年8月31日付 ※ ニュース見出し
【和文】
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN014VT0R00C21A7000000/
【英文】
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil
/US-completes-Afghanistan-troop-withdrawal-to-end-20-year-presence
–
◆ 「 存在 」 や 「 存在感 」 では、表現しきれない重厚な中身。
カタカナで表記せざるを得ない苦渋を、汲み取れる気がする。
無論、 もっと身近な普段使いの 「 存在 」 「 存在感 」 でも使える。
- ” Local residents expect to see an increased tourist presence
in the area.”
( 地元住民は、観光客が増えると予想している。)
– - ” There was a heavy police presence at the home.”
( その家には大勢の警官がいました。)
– - ” The place seemed to reject human presence.”
( その場所は人間の存在を拒絶するかのように思えた。)
– - ” There is a significant rodent presence at the location.”
( その場所にはかなりのネズミがいる。)
– - ” I didn’t realize the difference my presence can make
in someone’s life.”
( 私の存在が、誰かの人生にもたらす違いに気づいていなかった。)
( 私の存在が、誰かの人生に違いをもたらすことができるなんて。)
– - ” Your presence ensures success.”
( あなたの存在によって成功が約束される。)
– - ” The driver seems aware of her presence.”
( 運転手は彼女の存在に気づいているようだ。)
– - ” There is a presence about him.”
( 彼にはどこか存在感がある。)
– - ” She may have left physically, but her presence remains.”
( 肉体的には去ったかもしれないが、 彼女の存在感は残っている。)
– - ” I can feel the presence of my deceased dog.”
( 亡き愛犬がそばにいるような気がする。)
– - ” Our business doesn’t have an online presence.”
( 我が社にはインターネット上の存在感がない。)
– - ” She had good looks and a commanding presence.”
( 彼女は容姿端麗で威厳のある存在感であった。)
– - ” We need an influencer with a strong social media presence.”
( ソーシャルメディアで強い存在感を放つ インフルエンサー が必要だ。)
– - ” I stay out of the spotlight and limit my social media presence
to the bare minimum.”
( 目立つことを控え、ソーシャルメディア上の存在感を最小限に抑えている。)
– - ” Her presence is no longer politically sustainable.”
( 彼女の存在は、もはや政治的に持ちこたえられるものではない。)
– - ” Metal detectors are helpful in detecting the presence of
unauthorized weapons.”
( 金属探知機は、許可されていない武器の存在を検出するのに役立つ。)
– - ” His presence will be sorely missed.”
- ” His presence will be dearly missed.”
( 彼が存在しないことは、かなりの痛手である。)
( 彼が亡くなり、とても惜しまれる。)
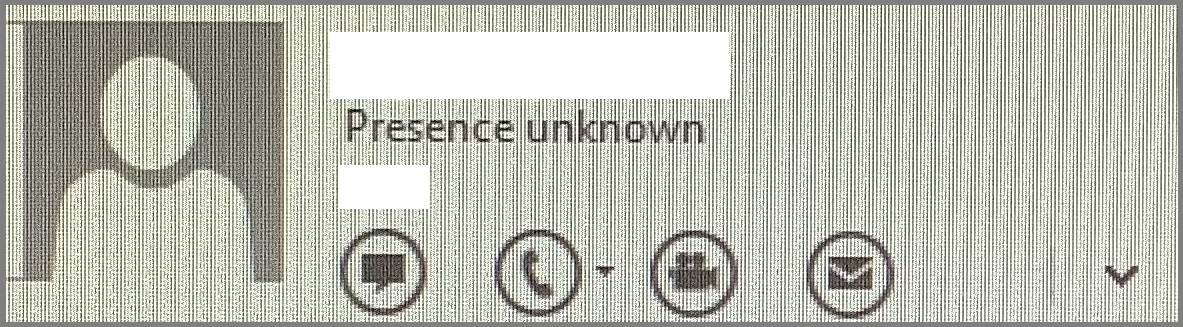
存在不明
–
※ 在籍しているかすら分からない
→ 現時点で Outlook は把握不能–
( 単に未接続 offline なだけだったりする )
–
◆ 報道価値 を考慮すれば、 「 存在感 」 と 「 存在 」 が主となる。
–
軍事関連では 「 駐留 」 も大事。
–
その他の語義は日頃使われるものの、ニュース沙汰にはなりにくい。
- 風采
- 出席
- 面前
- 舞台度胸
- 臨場感
◆ ” presence ” の語源は、 ラテン語 「 出席 」( praesentia )。
意味が広がっていった。
–
–
「 ~ の存在 する場所で 」
と言い換えれば、 これまた 「 存在 」 から想起できる。
–
- ” Her children were forced to celebrate Christmas
in the presence of their dead mother.”
( 子どもたちは、母親の亡骸の前でクリスマスを祝う
ことを強いられた。)
上掲の主な語義( 青字 )を網羅することが想定できよう。
–
< 核 > となる「 出席 」「 存在感 」「 存在 」で、 まず柱を立てる。
残りは、追々肉付けしていけばよい。–
–
こうした流れを取り入れると、単語学習が楽になる。
–
語源は、 発生順 の語義の配列をする辞書には、大抵載っている。
しかし、 頻度順 に配列する辞書の方が、< 核 > は分かりやすい。–
ゆえに、 一般的な英語学習者には、頻度順の方が実用的と考える。
学習者対象の 学習英英辞典(EFL辞典) は、 大方「 頻度順 」。
英語ネイティブ向けの英英辞典は 「 発生順 」 が目立つ印象。–
で詳述している。
–
–
–
◆ ” presence ” は、名詞のみ。
可算と不可算を兼ねるが、基本は不可算名詞。
なぜなら、< 核 > たる「 出席 」「 存在感 」「 存在 」が
不可算名詞であるから。
どちらも抽象的でつかみどころがない概念。
つまり、不可算名詞の「 抽象名詞 」( abstract noun )。
–
【参考】 ※ 外部サイト
・ 不可算名詞は「 物質 」「 抽象 」「 固有 」の3つ
・ 可算と不可算を見分ける簡単なコツ
・ 可算と不可算を兼ねる名詞について
・ 可算と不可算についてよくある質問–
–
–
◆ 4大学習英英辞典( EFL辞典 )に基づき、” presence ” の
可算・不可算を仕分けると、 原則は次の通り。
- 存在感 不可算
- 存在 不可算(または単数名詞)
- 風采 不可算
- 出席 不可算
- 面前 不可算
- 舞台度胸 不可算
- 臨場感 不可算
- 駐留 不可算
- プレゼンス 単数名詞
- 霊 可算
–
※ 「 単数名詞 」 = ” singular noun “
単数形で使われるのが一般的な名詞
このように不可算が圧倒的に優位である。
だから、「 基本は 不可算名詞 」。
◆ こうして、例文やら語義やら、数多く見てくると、
” presence ” は大した存在に思えてくる。
ところが、 英単語全体における立ち位置はそうでもない。
- 重要度:<3001~6000語以内>
- 書き言葉の頻出度:<2001~3000語以内>
- 話し言葉の頻出度:3000語圏外
( ロングマン、LDOCE6 )
【発音】 prézns
【音節】 pres-ence (2音節)
話し言葉がランク外であることは、先ほど記した
「 少々堅めの言い回し 」の裏付けのひとつになる。
すなわち、 政治・経済・軍事 の方面。
–
への言及は 必須となる。
有力な『 新編 英和活用大辞典 』及び
『 オックスフォードコロケーション辞典 』
は、下記の通り、たっぷり紙幅を割いている。
–
–
■ 名詞 “ presence ”
画像の拡大
ー
『 新編 英和活用大辞典 』(アプリ版)より転載
ー
” presence ” 1語のために、 このボリューム。
ちょいと見掛け倒しな重要度・頻出度であったはずなのに。
いくらなんでも、分不相応ではないか。
–
以下に似通う特色である。
どれほど重きを置かれているか。
ご紹介した例文から垣間見えるように、いつの時代も
勢力・権力にまつわる報道は重要視されるものである。
–
–
【関連表現】
- ” presence of mind ”
( 心の平静 )
「 心ここにあらず 」 ( absence of mind ) の逆。
「 心ここに 存在 ( presence ) する 」より。
–
Presence of mind ( 1660s ) is a loan-translation of
French présence d’esprit, Latin praesentia animi.
–
フランス語 ” présence d’esprit ” 及び
ラテン語 ” praesentia animi ” からの
借用翻訳 ( a loan-translation ) と書いてある。
” peace of mind ” に似た意味合い。
◇ 「 見出し 」英語の解説は、ここが秀逸 ↓
英語ニュースの読み方( 見出し編 )RNN時事英語