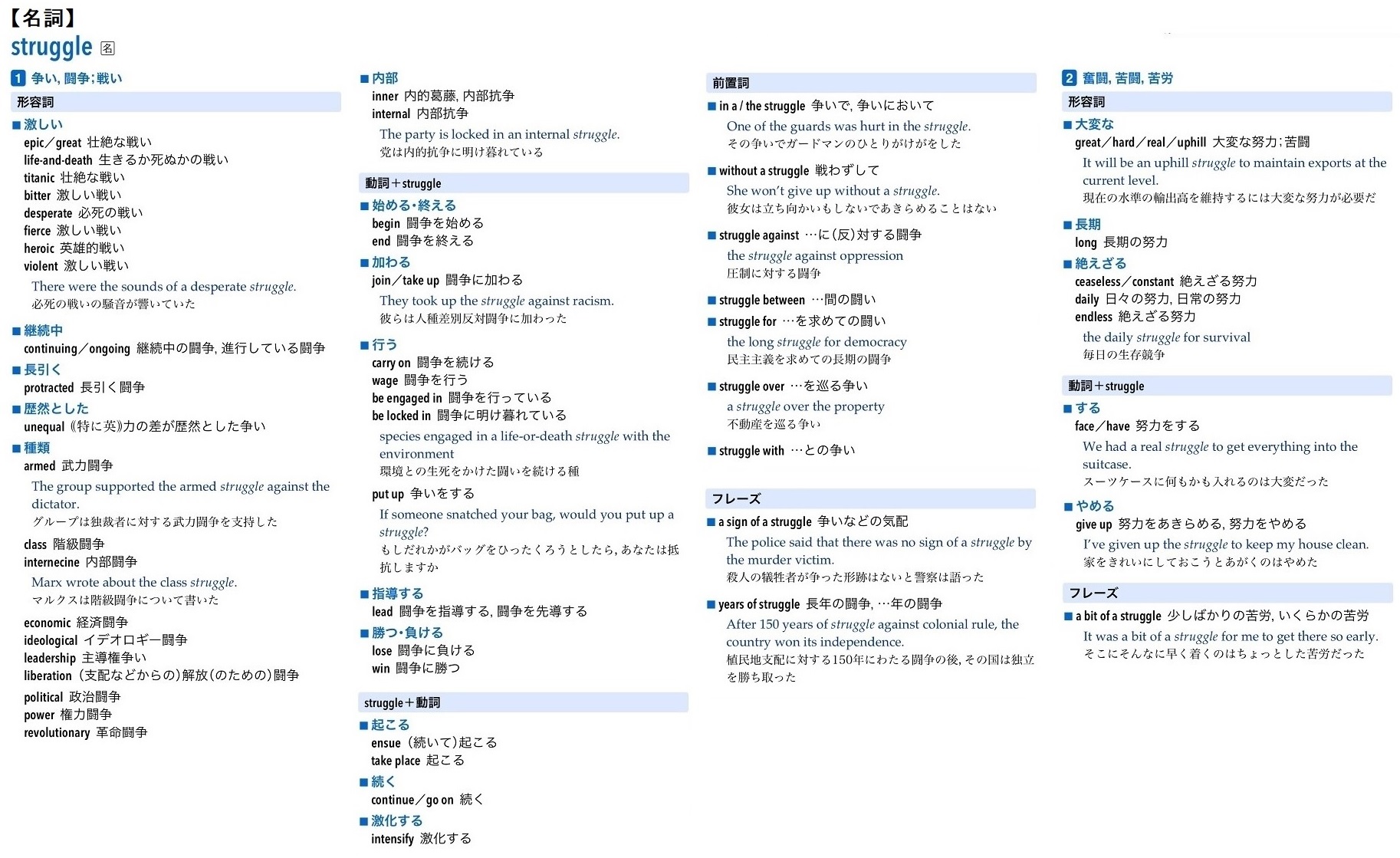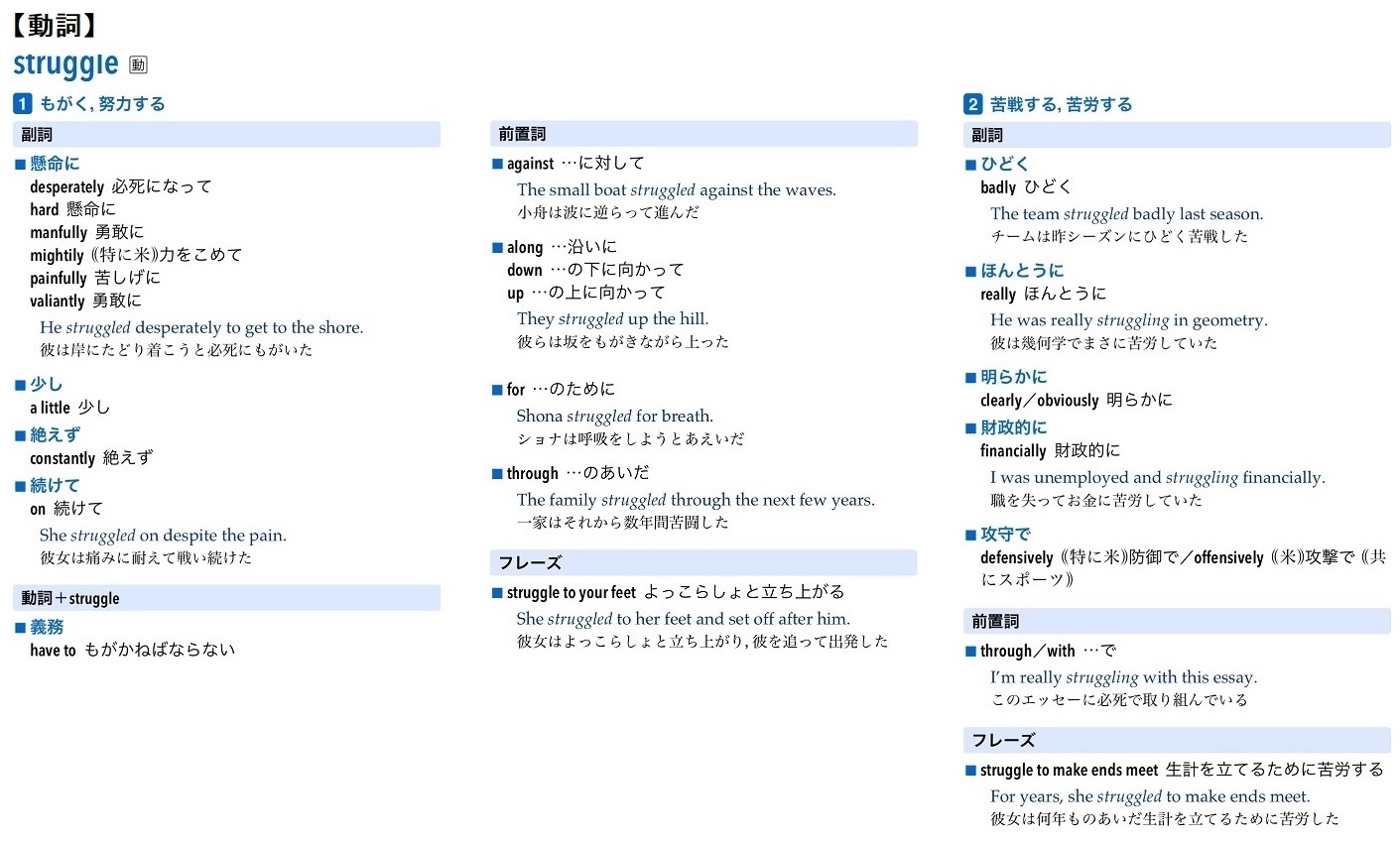Struggle
2026/01/01
努力( する )、 苦戦( する )
自他の頑張る姿 を表現する際に出てくる動詞・名詞。
【発音】 strʌ́gl
【音節】 strug-gle (2音節)
- 【相手】 老若男女 → 不問
- 【用途】 公私 → 不問
- 【場面】 硬軟 → 不問
- 【手段】 筆舌 → 不問
死に物狂いの真剣勝負はもちろんのこと、
じたばたもがく様子を面白おかしく描写するのに
用いてもOK。
–
◆ ” struggle ” には、動詞と名詞がある。
名詞は、可算名詞 ( countable noun )。
- ” Writing is not just a struggle.”
( 書くこととは、単なる苦労ではない。)
– - ” The mental struggle is still here.”
( 精神的な葛藤はまだ続いている。)
動詞は、 自動詞 ( intransitive verb )中心。
他動詞を省略している辞書が目立つ。
3大学習英英辞典( EFL辞典 )には、他動詞の記載がない。
断トツ で簡潔な語釈を示すのが次の辞書。
–
struggleverb [I]
– ( TRY HARD ) to work hard to do something.
– ( FIGHT ) to fight, esp. physically.
– ( MOVE ) to move with difficulty.noun [C]
– ( FIGHT ) a fight.
– ( TRYING HARD ) a very great effort to do something.( Cambridge Academic Content Dictionary )
【発音】 strʌ́gl
【音節】 strug-gle (2音節)
–
[I] = intransitive = 自動詞
[C] = countable = 可算名詞
–
” struggle ” については、この上ない分かりやすさ。
よって、3大EFL辞典 を差し置いてご紹介する。
まず、青字に着目。
–
< 自動詞 > intransitive verb
- try hard ( 努力する )
- fight ( 苦戦する、苦労する )
- move ( もがく )
< 可算名詞 > countable noun
- fight ( 争い、闘争、戦い )
- trying hard ( 奮闘、苦闘、苦労 )
–
” struggle ” の骨子は、これがすべて。
カッコ内の和訳は後述の
『 オックスフォード 英語コロケーション辞典 』( アプリ版 )
を適用した。
” struggle ” は頻出の感があるが、 英単語全体からはそうでもない。
LDOCE6( ロングマン )の指標では、 動詞・名詞とも、
- 重要度 : 3001~6000語以内
- 書き言葉の頻出度 : 2001~3000語以内
- 話し言葉の頻出度 : 3000語圏外
◆ 語源は、 中期英語 「 もがく 」( struglen )。
–
もがく【踠く】
1. 苦しがって手足を動かす。
2. あせり苦しむ
( 三省堂国語辞典 第八版 )
–もがく【踠・藻掻】 (「 藻掻 」 はあて字 )
1. もだえ苦しんで手足を動かす。 あがく。
2. いらだつ。 あせる。 じりじりする。
( 精選版 日本国語大辞典 )
–
先の青字 ” MOVE ” は、手足のばたばたが該当する。
もぞもぞ緩慢に動くのではなく、 派手にバタつく行為。
例えば、 「 水中でもがく 」 「 羽交い締めにされてもがく 」。
しかし、 溺れかけたり、 羽交い締めにされる機会はそうそう生じない。
ゆえに、 実際の「 もがく 」 は 「 もだえ苦しむ 」 意味で多用される。
したがって、 「 もがく 」 と ” struggle ” の日常用法としては、
「 2 」 の用途が一般的。
–
すなわち、
” try hard “( 努力する ) 及び ” fight “( 苦戦する、苦労する )。
同様に、 名詞 ” fight “( 争い、闘争、戦い )も、 非日常的に近い。
” trying hard “( 奮闘、苦闘、苦労 ) の方が普通。
こう見てくると、 ” struggle ” は 「 もがく 」 と重なることが分かる。
日英もろとも、 意味合いと使われ方が似通っている。
–
◆ 戦争や事故・災害時などの非常時の情報であれば、
「 闘争 」「 戦い 」「 苦しがって手足を動かす 」 を指す確率
が上がるのは言うまでもない。
日頃、 一般人が用いる機会が比較的少ないため、 本稿では
後回し にしたものの、 ニュースや論文などには出てくる。
意味が明確で混乱しにくい点も、 優先順位 を繰り下げる要因となった。
これ以外の ” struggle ” は、 上掲の青ハイライトの意味中心となる。
私たち日本人が普段使ったり、 見聞きしたりする際も同様である。
したがって、 本稿ではこれらの語義に焦点を当てる。
–
” struggle ”
- try hard ( 努力する )
- fight ( 苦戦する、苦労する )
- trying hard ( 奮闘、苦闘、苦労 )
–
動詞と名詞の意味合いは重なるので、以下まとめて論じる。
この表を二分すると、
-
努力する → 奮闘
-
苦戦する → 苦闘
◇ 「 苦労する → 苦労 」 は概ね双方に該当するため、ここでは除外
日本語の 1 と 2 では、 受け手の印象に差が生じるだろう。
一見大差ないように思えるが、「 苦闘 」 と 「 奮闘 」はやはり違う。
「 奮闘 」 は 「 がんばっているな 」 で済まされても、
「 苦闘 」 は 軽々しく口にできない雰囲気。
–
どっちも必死だが、 「 苦闘 」 はかなり苦しい努力を指す。
例えば、
- 「 1. 受験勉強に奮闘する 」 vs 「 2. 受験勉強に苦闘する 」
- 「 1. 婚活に奮闘する 」 vs 「 2. 婚活に苦闘する 」
2は、 ご当人のしんどさがビシビシ伝わってくる。
つらくて、 笑顔が一気に消え失せる感じ。
悲壮感が漂い、 とてもとても ジョークにできない。
” struggle ” は、 1と2の両方とも意味するため、
和訳時は内容を読み取って区別する。
前置詞で区分できる場合もあるが、 多用される前置詞
のほとんどが共通する。
–
すなわち、
- for
- with
- against
- on
- to
–
※ 後掲 「 コロケーション辞典 」 参照
そのため文脈から見分けるのが基本となる。
ところが、1、2のどちらなのか、 明確でない場面も多い。
つまり、 いずれの解釈もありうる内容が普通に存在する。
翻訳者の立場からも、 あいまいすぎて迷う案件が少なくない。
–
◆ 日本人にとって、” struggle ” が厄介なのは、 このように
和訳時に迷いが生じやすい点にある。
努力している有様は看取できるが、 なんだかはっきりしないのだ。
–
「 この人にとって、どの程度 きついのだろう 」
–
ご本人でないのだから、 推し量りがたいのは当然である。
「 受験勉強 」 と 「 婚活 」 の例からも感じ取れるように、
和訳によって、 受け手の認識は左右される。
どの程度なのか判明しない限り、 判断は難しい。
結局、「 苦闘 」 に至る苦労か否かは、 総合的に決めることとなる。
–
◆ 一方、 ” struggle ” の使い手側はどうか。
–
日常用法については、 厳密に判別することなく使っている
可能性が高いと考えられる。
「 奮闘 」であろうと「 苦闘 」であろうと、 無我夢中の
真っ最中に細かい差異を意識する余裕はないもの。
思い出す時ですら、 区別はそれほど意味をもたない。
とにかく 「 苦労 」 が伴う姿を伝えたい …
これぞ使い手の意図であり、 ” struggle ” の真骨頂。
” offensive ” でも取り上げたように、 使い手自身も今ひとつ
自覚していない場合が珍しくなかったりする。
” struggle ” がこれらの語義を包括する 以上、
きっちり区別すること自体が不自然な話なのかもしれない。
少なくとも、 普段遣いでは深く考えたりしないのが大勢。
英語学習者は、 的確な「 和訳 」をあれこれ考える習慣がある。
だからこそ、 上記のような迷いが生じる。
日本語で理解する上では、 欠かせないプロセスである。
それでも、 ” struggle ” を駆使するレベルの英語力が身につけば、
区別を執拗に考える意義を見出せなくなっていく。
「 努力する 」 意をひっくるめた ” struggle ” を使うのに、
日本語でああだこうだは、ちょっと変。
いちいち和訳なんてするかよ …
自ずとこんな感覚になっていたりする。
母語を介さず、 英語のまま理解できるようになってくると、
このような思いをすることもしばしば。
–
日本人の英語学習者としては、 良し悪しの現象である。
【参照】
・ 対となる日本語がなければ、イメージで理解
・ 日本語にない文法は、原文で慣れる
–
◆ ニュースなどメディア報道の用途ではなく、
ずっと身近な使い方を挙げてみる。
これまで述べてきた意味の区別に気を使うべきかどうか、
それぞれ考えていただければと思う。
和訳は一例である。
–
ー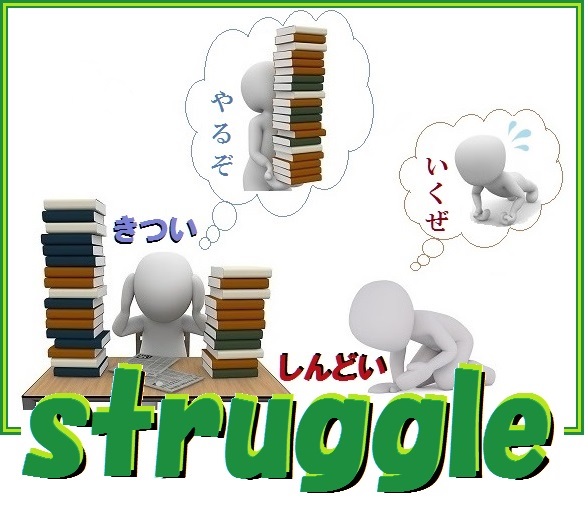
- ” I struggled with my research on this article.” ↑ 上図
( この記事の下調べに苦労しました。)
– - ” I struggle to do knuckle push-ups.” ↑ 上図
( 拳腕立て伏せに苦戦しています。)
– - ” He struggles financially.”
( 彼は経済的に苦労している。)
– - ” I knew John struggled with his demons for years.”
( ジョンが個人的な悩みに長年苦しんでいたことは知っていました。)
– - ” She struggled all the time during her school years.”
( 彼女は学生時代に絶えず苦しんでいました。)
– - ” We are struggling with rising grocery costs.”
( 食料品の価格高騰に苦しんでいます。)
– - ” It’s been a struggle and a journey.”
( 苦しみの連続であり、 旅路でもあった。)
– - ” Each day is a struggle against pain.”
( 毎日が痛みとの戦いです。)
– - ” We are struggling to find a balance between
health and economy .”
( 健康と経済のバランスを見出すべく努めています。)
– - ” I’m struggling to balance my work and family life.”
( 仕事と家族とのバランスを取るため、格闘しています。)
– - ” Listeners can feel her inner struggle as she sings.”
( 彼女の歌を聴くと、彼女の内面の葛藤を感じ取れる。)
– - ” They struggled with all the fame.”
( 名声を得て、彼らは苦しんだ。)
– - ” He is struggling to reinvent himself.”
( 彼は自己改革しようと躍起になっている。)
– - ” She struggles with alcoholism and depression.”
( 彼女は、アルコール依存症と抑うつに苦しんでいる。)
– - ” The military is struggling to stem infections.”
( 軍は感染の阻止に苦労している。)
– - ” I’m struggling to keep things positive these days.”
( この頃は、物事をポジティブに保つべく苦労している。)–
–
- ” Surviving on a single salary can be a struggle.”
( 共働きでない場合、苦労もありえます。)
– - ” She struggled to find a place in Hollywood as she got older.”
( 年を取るにつれ、彼女はハリウッドで居場所を見つける
のに苦労した。)
– - ” I struggled for words.”
( 必死に言葉を探しました。)
– - ” They struggle with self-respect.”
( 彼らは自尊心の面で苦しんだ。)
– - ” I struggled to recall where I recognized him from. ”
( 彼に見覚えはあるものの、どこで見たか思い出すのに手間取った。)
– - ” Mary opened up about her struggles in Japan.”
( メリーは日本における苦労について打ち明けた。)
– - ” Erika got candid about her substance abuse struggles.”
( エリカは薬物乱用との闘いについて率直に語った。)
– - ” We struggled hard for workplace improvement.”
( 職場改善に向けて、我々は奮闘しました。)
– - ” She struggles with exam stress.”
( 彼女は試験のストレスに苦しんでいる。)
– - ” He struggled on despite his mental health problems.”
- ” He kept going despite mental health struggles.”
( 心の問題があるにもかかわらず、彼は頑張り続けた。)
– - ” I struggled with feelings of shame for most of my life.”
( 恥の意識に苦悩し続ける人生を送ってきた。)
– - ” The world struggles against a deadly coronavirus pandemic.”
( 世界中が致命的なコロナウイルス感染症の大流行と闘っている。)
– - ” I struggled to gain freedom from my toxic parents.”
( 毒親から自由になるため、私は戦った。)
– - ” Japan struggles to contain further spread of the virus.”
( ウイルスをこれ以上拡散しないよう、日本は奮闘している。)
– - ” Japan is struggling to slow the spread of the disease.”
( この病気の蔓延を遅らせるのに、日本は苦慮している。)
– - ” X gave up altogether after years of struggling to ramp up output.”
( X社は、生産高を上げようと何年も奮闘した後、完全に手を引いた。)
– - ” Local governments struggling with applications for virus cash”
( 地方自治体、コロナ給付金の申請で大混乱)
※ ニュース見出し
–
◆ 形容詞 ” struggling ” の意味合いも変わらない。
【発音】 ˈstrʌɡ.lɪŋ
【音節】 strug-gling (2音節)
- ” She used to be a struggling author.”
( かつて彼女は奮闘する作家であった。)
( かつて彼女は売れない作家であった。)
– - ” She used to be a single mom struggling to
make ends meet.”
( 彼女は家計のやりくりにもがくシンママであった。)
– - ” Their struggling economy needs government help.”
( かの国の苦しい経済は政府支援を必要としている。)
– - ” Japan’s government approves cash handout for
struggling students amid pandemic”
( 日本政府、パンデミックで苦しむ学生のための給付金を決定)
※ ニュース見出し
–
◆ 前置詞の話で、 コロケーション辞典に触れた。
–
『 オックスフォード コロケーション辞典 』 がこちら。
コロケーション辞典の代表格である。
–
–
■ 動詞 ” struggle ““ Oxford Collocations Dictionary for
Students of English “ ( アプリ版 )より転載※ 漢字は追加
–
” struggle ” については、 底本の英語版に比べ、
日本語版の方が充実した内容。
英語版にない名詞 ” struggle ” も、 日本語版は詳説する。
–
–
■ 名詞 ” struggle “画像の拡大
–
–
■ 動詞 ” struggle “
『 小学館 オックスフォード 英語コロケーション辞典 』
( アプリ版 )より転載
–
◆ コロケーション辞典は、当該単語の前後で用いられる
言葉を品詞ごとに具体的に列挙する。
英語学習者は、 とりわけ前置詞に迷うケースが多い。
” struggle for ” なのか、 ” struggle with ” なのか。
意味に違いがあるのか。
あやふやな基礎知識を手っ取り早く確認できる上、
作文に行き詰まった時は慈雨となる。
表現が思いつかず ” struggle ” する時は、 適宜真似るとよい。
そっくりそのまま、 もらい受けてしまおう。
同時に、 自分の語彙に追加しておく( 語彙採集 )。
このプロセスを繰り返すと、 力量が上がる。
もっとも、 主要単語の場合、学習英英辞典( EFL辞典 )
にも、 コロケーションは併記されていることが多い。
特に、 “ LDOCE ” と “ OALD ” は、 コロケーション満載。
–
【実例】 ※ 辞書アプリの転載あり
threshold、 damage、 scrutiny、
backdrop、 paperwork、 downfall、
bombshell、 alternative、 feasible、
disparity、 presence
–
◆ 日本語のコロケーション辞典は、 『 てにをは辞典 』( 三省堂 )
をお勧めしたい。 → 写真
書籍版と 「 自炊 」 した電子版を併用しているが、 大変便利。
◇ 使用 ipad mini → 写真 ( 辞書の 「 自炊 」 と辞書アプリ )
日英のコロケーション辞典がないと、 弊ブログは立ち行かない。